|
|
|
京都歴史災害年表(自然災害・人災) 1
1 古墳時代-平安時代前期(3世紀中期-899) |
| *作成中 |
  |
  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
⇒古墳時代 ⇒飛鳥時代 ⇒奈良時代 ⇒平安時代前期
1 古墳時代-平安時代前期(3世紀中-899) 2 平安時代中期(901-1000) 3 平安時代後期 1(1001-1100) 4 平安時代後期 2(1101-1184) 5 鎌倉時代 1(1185-1230) 6 鎌倉時代 2(1231-1332) 7 南北朝時代(1333-1392) 8 室町時代前期(1393-1429) 9 室町時代中期(1430-1466) 10 室町時代後期(1467-1572) 11 安土・桃山時代(1573-1602) 12 江戸時代前期(1603-1709) 13 江戸時代中期(1710-1786) 14 江戸時代後期(1787-1867) 15 近代(1868-1945) 16 現代(1945-)
 地震・津波 地震・津波  大雨・長雨・洪水 大雨・長雨・洪水  台風・大風など 台風・大風など  雷 雷  旱魃・酷暑 旱魃・酷暑  大雪・雹・寒冷など 大雪・雹・寒冷など  山崩・土砂崩 山崩・土砂崩  凶作・不作 凶作・不作  虫害・獣害 虫害・獣害  飢饉・窮乏・賑給 飢饉・窮乏・賑給  疫病・疾病など 疫病・疾病など  火災 火災  戦乱・一揆・強訴 戦乱・一揆・強訴  事件・事故など 事件・事故など  公害・環境 公害・環境  土木など 土木など
*おもな事項を掲載しています。年月日時・被害状況などは不確定な場合があります。括弧内の年月日は旧暦。 |
| ⇒国立天文台 日本の暦日データベース |
◆古墳時代 3世紀中・後期-7世紀前半
■4世紀(301-400)前期 ▣山科中臣村落の火事、竪穴式住居多数焼亡。(『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)
■5世紀(401-500)後期 ▣秦氏、葛野大堰築造。
◆飛鳥時代 507-710
■599年(推古天皇7年) ▣ユリウス暦5月26日・グレゴリオ暦5月28日(旧暦4月27日)「推古地震」。震央など詳細不明。大和震度6弱?。「地動、屋舎悉懐」。家屋倒壊し、日本で歴史に記録された最古の被害地震とされる。(『日本書紀』『大日本史』「 地震インフォ」) 地震インフォ」)
■646年(大化2年) ▣僧・道登/道昭?、宇治川に架橋。(「宇治橋造橋断碑」『続日本紀』)
■670年(天智天皇9年) ▣ユ5月24日・グ5月27日(4月30日)近畿雷震。(『京都気象災害年表』)
■684年(天武13年) ▣ユ11月26日・グ11月29日(10月14日)諸国大地震。「京都及諸国大震嘯起」。詳細不明。(『日本書紀』)
■691年(持統5年) ▣(6月)京都、郡国四十に雨水降る。(『日本書紀』『日本災変通志』)
■698年(文武2年) ▣(3月7日)越後国で疫病。医薬給し救援。(『続日本紀』『疫病の古代史』)
◆奈良時代 710-794
■701年(文武5年/大宝元年) ▣ユ5月8日・グ5月12日(3月26日)「丹波地震三日」「丹波地震」「大宝地震」。地震(規模不明)、京都府北部、若狭湾内の冠島・沓島島が山頂のみを残して海中に没した。記録に残る最古の例、後世の記録とされ信憑性は乏しいとも。(『続日本紀』『類聚国史』、8世紀中の『丹後国風土記』、『日本歴史災害事典』「 地震インフォ」) 地震インフォ」) ▣(4月20日条)山背などで「連雨」。(『続日本紀』) ▣(4月20日条)山背などで「連雨」。(『続日本紀』) ▣ユ9月20日(8月14日)近畿大風・高潮。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月20日(8月14日)近畿大風・高潮。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ9月27日・グ10月1日(8月21日)17カ国大風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月27日・グ10月1日(8月21日)17カ国大風。(『京都気象災害年表』)
■702年(大宝2年) ▣(7月8日)山背国乙訓郡火雷神(向日神社)、祈雨に霊験あり、以後大幣・月次幣の例に入れる。(『続日本紀』『京都の歴史10
年表・事典』) 
■707年(慶雲4年) ▣ユ6月25日(5月21日)畿内霖雨・賑給。(『京都気象災害年表』) 
■708年(慶雲5年/和銅元年) ▣(3月2日)山背国に疫病流行、薬給し療せしめる。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)
■709年(和銅2年) ▣ユ7月1日(5月20日)近畿東海霖雨。山背国など連日の雨で苗を損じる。(『続日本紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) 
■733年(天平5年) ▣ユ2月25日(2月7日)近畿四国旱損。(『続日本紀』『京都気象災害年表』)
■734年(天平6年) ▣ユ5月14日・グ5月18日(4月7日)「地地震、盧舎壊厭死多」(『続日本紀』)、「天平地震(畿内七道地震)」近畿地方、M7、死者多数。生駒断層直下型。(『続日本紀』「 地震インフォ」) 地震インフォ」)
■735年(天平7年) ▣(8月)豌豆瘡(わんずかさ/えんどうそう、天然痘)流行し死者多数の報告あり。「天然痘(痘瘡、もがさ)」「赤疱瘡(あかもがさ)」とも呼ばれた。「はしか(麻疹)」も流行。(2月)新羅使入京、(4月)に唐より帰国した遣唐使一行(多治比広成・吉備真備ら)により、大宰府管内で流行発生、全国に感染広がる。新羅渡航以前に感染していたとも。読経・賑給・薬支給。長門以還で道饗祭(みちあえのまつり)実施。(9月)平城京で一品新田部親王、(11月)賀茂比女・知太政官事舎人親王、(閏11月)高田王ら4人が相次ぎ罹患し死亡。京都での詳細不明。(『続日本紀』『疫病の古代史』『平安京の災害史』)  ▣この年、天下疫病流行。凶作。(『続日本紀』) ▣この年、天下疫病流行。凶作。(『続日本紀』) 
■737年(天平9年) ▣(正月)遣新羅使ら鬼病(疫病)相次ぎ入京できず。(『続日本紀』) ▣春 筑紫(つくし)から疱瘡(天然痘)が伝染し、夏-秋に大流行。(『続日本紀』) ▣春 筑紫(つくし)から疱瘡(天然痘)が伝染し、夏-秋に大流行。(『続日本紀』) ▣(4月-)京畿内で疫病流行、地方でも流行か。(4月)藤原房前が疫死。(『類聚符宣抄』巻三、『疫病の古代史』) ▣(4月-)京畿内で疫病流行、地方でも流行か。(4月)藤原房前が疫死。(『類聚符宣抄』巻三、『疫病の古代史』) ▣(5月)宮中で大般若経読経、疫病収束祈願。 ▣(5月)宮中で大般若経読経、疫病収束祈願。 ▣(6月1日)大宅大国ら官人11人の相次ぐ疫病罹患・死亡により朝廷の儀式をやめる。(『続日本紀』『疫病の古代史』) ▣(6月1日)大宅大国ら官人11人の相次ぐ疫病罹患・死亡により朝廷の儀式をやめる。(『続日本紀』『疫病の古代史』) ▣(6月26日)赤班瘡(麻疹)流行とも。(『類聚符宣抄』) ▣(6月26日)赤班瘡(麻疹)流行とも。(『類聚符宣抄』) ⋄疫病流行に対し、太政官より諸国国司に対処法通達下される。(『類聚符宣抄』巻三、『疫病の古代史』) ⋄疫病流行に対し、太政官より諸国国司に対処法通達下される。(『類聚符宣抄』巻三、『疫病の古代史』) ▣疫病流行のため、典薬寮、貴族対象に治療法・湯薬調合法など作成。(『疫病の古代史』) ▣疫病流行のため、典薬寮、貴族対象に治療法・湯薬調合法など作成。(『疫病の古代史』)
■742年(天平14年) ▣ユ6月9日(5月3日)近畿水損。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月11日(6月5日)山城怪雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月11日(6月5日)山城怪雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月14日(9月12日)山城大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月14日(9月12日)山城大風雨。(『京都気象災害年表』) 
■743年(天平15年) ▣ユ3月-6月(3月-5月)山城不雨。(『京都気象災害年表』) ▣(6月26日)山背国司、宇治川が(24日)に歩いて渡れるほどに渇水したと言上す。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(6月26日)山背国司、宇治川が(24日)に歩いて渡れるほどに渇水したと言上す。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)
■754年(天平勝宝6年) ▣ユ8月(8月23日)畿内風水。(『京都気象災害年表』) 
■756年(天平勝宝8年) ▣(4月)京畿内に麻疹流行。
■760年(天平宝字4年) ▣(9月)この頃、全国的に豌豆瘡(天然痘)が流行。京畿内不明。(『続日本紀』『疫病の古代史』)  
■762年(天平宝字6年) ▣(5月4日)京都、畿内など飢う、賑給。 (『続日本紀』)
■763年(天平宝字7年) ▣(6月)京都疾疫流行。山背(城)・摂津疫す。疫病流行し賑給。 (『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) 
■764年(天平宝字8年) ▣(8月14日)畿内旱のため、造池使を遣し山背・丹波・近江などに池を築かせる。(『続日本紀』『日本紀略』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) 
■765年(天平宝字9年/天平神護元年) ▣(2月4日)山背など飢う。賑恤を加う。 (『続日本紀』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(2月)京都米価高し。西海道諸国、恣に私米を運漕。 (『続日本紀』『日本災変通志』) ▣(2月)京都米価高し。西海道諸国、恣に私米を運漕。 (『続日本紀』『日本災変通志』)
■767年(天平神護3年/神護景雲元年) ▣(2月17日)山背国飢う、賑給。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)
■770年(神護景雲4年/宝暦元年) ▣(7月15日)京都疾疫流行。京内諸寺で疫病・変異を除くため『大般若経』輪読命じる。(『続日本紀』『日本歴史災害事典』) ▣(10月1日)第49代・光仁天皇践祚。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月1日)第49代・光仁天皇践祚。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』)
■772年(宝亀2年) ▣(6月19日) 京都あちこちに隕石、大きさは柚子の如し、数日して止む。(『続日本紀』『日本災変通志』)
■773年(宝亀4年) ▣丹後国で疫病。(『続日本紀』『疫病の古代史』)
■774年(宝亀5年) ▣(2月13日)京都飢う、賑給。(『続日本紀』『日本災変通志』)
■777年(宝亀8年) ▣冬、雨降らず、井水涸れ宇治川など徒渉できる。取水する。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)
■781年(宝亀12年/天応元年) ▣(4月3日)第50代・桓武天皇践祚。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』)
■784年(延暦3年) ▣(10月30日)京中盗賊多く、隣保を作り検察させる。(『続日本紀』『日本史総合年表』)
■785年(延暦4年) ▣(9月23日)造長岡宮使・藤原種継、大伴継人らにより射られ、翌日没。(『続日本紀』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)
■788年(延暦7年) ▣ユ5月12日(4月3日)山城大旱。(『京都気象災害年表』) ▣ユ11月4日(10月2日)山城大雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ11月4日(10月2日)山城大雷雨。(『京都気象災害年表』) 
■790年(延暦9年) ▣ユ7月7日(5月21日)畿内大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(9月)京畿内に飢饉。翌年(10月)まで続く。(『続日本紀』『疫病の古代史』『日本史総合年表』) ▣(9月)京畿内に飢饉。翌年(10月)まで続く。(『続日本紀』『疫病の古代史』『日本史総合年表』) ▣秋-冬 京畿内・諸国に天然痘(豌豆瘡、疱瘡、裳瘡)流行。30歳以下の男女問わず多く病臥死亡。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』『疫病の古代史』『日本史総合年表』) ▣秋-冬 京畿内・諸国に天然痘(豌豆瘡、疱瘡、裳瘡)流行。30歳以下の男女問わず多く病臥死亡。(『続日本紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』『疫病の古代史』『日本史総合年表』)
■791年(延暦10年) ▣長岡京東南境界祭祀で墨書人面土器を用い、前年の近畿で流行した天然痘が長岡京に侵入するのを防ぐために、何らかの境界での祭祀が行われていたとみられている。(長岡京東南境界祭祀遺跡の出土木簡)
■792年(延暦11年) ▣ユ2月25日(1月29日)山城白気(白い雲気)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月24日(6月1日)山城寒冷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月15日(6月22日)山城大雷雨。長岡京の式部省南門、激しい雷雨・洪水で倒れる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ7月15日(6月22日)山城大雷雨。長岡京の式部省南門、激しい雷雨・洪水で倒れる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ8月30日(8月9日)山城大風洪水。大雨・洪水で桂川等あふれる。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月30日(8月9日)山城大風洪水。大雨・洪水で桂川等あふれる。(『京都気象災害年表』) ▣(8月10日)長岡京大洪水。 ▣(8月10日)長岡京大洪水。 ▣(8月11日)第50代・桓武天皇は紀伊郡赤目崎で洪水を見、翌日に水害にあう百姓に賑給。(『京都事典』) ▣(8月11日)第50代・桓武天皇は紀伊郡赤目崎で洪水を見、翌日に水害にあう百姓に賑給。(『京都事典』)  ▣ユ12月12日(11月24日)山城初雪・大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月12日(11月24日)山城初雪・大雪。(『京都気象災害年表』)
■793年(延暦12年) ▣ユ12月19日(11月12日)山城大雪。(『京都気象災害年表』)
◆平安時代前期 794-1185
■794年(延暦13年) ▣ユ8月9日(7月10日)山城落雷。「宮中並びに京畿官舎及び人家震う。或いは震死する者あり」南海地震とみられる巨大地震が起きていたともいう?。震死とは落雷による死亡という。(『日本後紀』などの内容を抜粋した『日本紀略』『山城志』『日本災変通志』『京都気象災害年表』)  ? ?
■795年(延暦14年) ▣ユ2月7日(1月13日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月29日(閏7月11日)京都大風。官舎・京中屋破壊。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ8月29日(閏7月11日)京都大風。官舎・京中屋破壊。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)
■796年(延暦15年) ▣ユ5月26日(4月15日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月21日(5月12日)京都大雨洪水。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ6月21日(5月12日)京都大雨洪水。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月11日(8月6日)近畿霖雨水損。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月11日(8月6日)近畿霖雨水損。(『京都気象災害年表』) ▣(8月7日-8日/8日)大雨により穀価騰貴、京中百姓に賑給。(『日本紀略』前篇十三、『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(8月7日-8日/8日)大雨により穀価騰貴、京中百姓に賑給。(『日本紀略』前篇十三、『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) 
■797年(延暦16年) ▣ユ9月9日(8月14日)畿内で地震・暴風。京都大風。左右京坊門、百姓屋など多く倒れる。平安京での被害は少なかったとも。奈良・東大寺大仏の首、崩落。(『日本紀略』『類聚国史』『日本後紀』『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』)  ▣翌年ユ1月5日(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月5日(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■798年(延暦17年) ▣ユ9月23日(8月9日)京都大風。京中、大風により百姓盧舎壊。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)
■799年(延暦18年) ▣ユ4月10日(3月1日)落雷。民部省の廩(蔵)に震(落雷)。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)
 ▣ユ5月18日(4月9日)近畿水損。勅、澇水(洪水)により苗稼腐損、窮弊の民、更めて播くことを得ず。山城などの貧民巡検し正税を以て給せしむ。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ5月18日(4月9日)近畿水損。勅、澇水(洪水)により苗稼腐損、窮弊の民、更めて播くことを得ず。山城などの貧民巡検し正税を以て給せしむ。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣(4月15日)左右京貧民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月15日)左右京貧民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(7月17日)丹後国飢う。賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月17日)丹後国飢う。賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』)  ▣ユ10月10日(9月7日)京都暴風。京中屋舎顛倒するもの多し。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ10月10日(9月7日)京都暴風。京中屋舎顛倒するもの多し。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)

■800年(延暦19年) ▣(10月4日)山城・大和など6国の諸国民1万人徴発により葛野川の堤修造。(『日本紀略』『日本災変通志』『日本史総合年表』)
■802年(延暦21年) ▣(6月12日)京都大火、左京大火。左京百姓宅42烟焼失、米塩給す。(『日本紀略』前篇十三、『京都事典』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』)
■804年(延暦23年) ▣ユ4月29日(3月16日)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(5月20日)山城国穀4000斛、左右京高年に賑給。(『日本後紀』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(5月20日)山城国穀4000斛、左右京高年に賑給。(『日本後紀』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ9月17日(8月10日)京都・近畿暴風雨。暴風雨により、中院西楼倒れ、神泉苑左右閣、京中民家多く倒れる。(『日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ9月17日(8月10日)京都・近畿暴風雨。暴風雨により、中院西楼倒れ、神泉苑左右閣、京中民家多く倒れる。(『日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) 
■805年(延暦24年) ▣ユ12月31日(12月7日)第50代・桓武天皇の勅命により、殿中で参議右衛士督・藤原緒嗣と参議左大弁・菅野真道に天下の徳政を論じさせる。緒嗣、天皇肝入りの軍事(蝦夷征討)と造作(平安宮造営)中止を進言。天皇、両事業の停止決定。(徳政相論)。復興遅延に伴うこの大規模救恤は既定路線だったとも。(『日本後紀』『疫病の古代史』)
■806年-810年(大同元年-5年) ▣大同年中、穀倉院(二条南、朱雀西)を初めて置き、畿内諸国の銅銭・無主位田・職田・没官田などの穀を収め、貧民・飢民に賑恤。(『西宮記』『京都の歴史10
年表・事典』)
■806年(延暦24年/大同元年) ▣(3月17日)第51代・平城天皇践祚。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月22日)大井・比叡・小野・栗栖野など山火事、烟灰四もに満ちて京中、昼も昏し。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(閏6月8日)葛野郡大井山の材木伐採禁じる。この大井川(嵐山)河岸の伐木禁止令布達は、日本初の砂防の始まりとされている。(『日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』「 ▣(閏6月8日)葛野郡大井山の材木伐採禁じる。この大井川(嵐山)河岸の伐木禁止令布達は、日本初の砂防の始まりとされている。(『日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』「 京都府建設交通部砂防課」) 京都府建設交通部砂防課」) ▣(閏6月)葛野郡大井は河水暴流すれば堰堤淪没す。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(閏6月)葛野郡大井は河水暴流すれば堰堤淪没す。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月)防葛野河使、内親王・命婦をして、葛野川を掘る役夫(開削)を進める。(『日本後紀』『平安京の災害史』) ▣(7月)防葛野河使、内親王・命婦をして、葛野川を掘る役夫(開削)を進める。(『日本後紀』『平安京の災害史』) ▣ユ9月19日(8月4日)近畿水害。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月19日(8月4日)近畿水害。(『京都気象災害年表』) ▣(9月4日)左右京の堤溝修理。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(9月4日)左右京の堤溝修理。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(9月23日)水旱による米価騰貴防止のため、左右京・山崎津・難波津の酒屋の甕を封じる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(9月23日)水旱による米価騰貴防止のため、左右京・山崎津・難波津の酒屋の甕を封じる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(11月)京都大洪水。鴨川・大堰川修造。(『日本歴史災害事典』) ▣(11月)京都大洪水。鴨川・大堰川修造。(『日本歴史災害事典』) 
■807年(大同2年) ▣ユ6月10日(5月1日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月23日(6月15日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月23日(6月15日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣(11月17日)大堰修理。(『日本後紀』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月17日)大堰修理。(『日本後紀』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月25日)京都疾疫流行。京中疫者流行し、病人に賑給。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(12月25日)京都疾疫流行。京中疫者流行し、病人に賑給。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) 
■808年(大同3年) ▣(1月7日)京都疾疫流行。京中疫病百姓に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』)  ▣(1月12日)京都疾疫流行。使を遣し医薬により京中病人を治む。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(1月12日)京都疾疫流行。使を遣し医薬により京中病人を治む。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(1月13日)京都疾疫流行。京中病死者死骸を埋葬、病人に賑給。勅に近頃疫癘熾ん、死亡やや多し。諸大寺、畿内七道諸国に大般若経を奉読せしむ。(『類聚国史』『日本紀略』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(1月13日)京都疾疫流行。京中病死者死骸を埋葬、病人に賑給。勅に近頃疫癘熾ん、死亡やや多し。諸大寺、畿内七道諸国に大般若経を奉読せしむ。(『類聚国史』『日本紀略』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(2月24日)京都疾疫流行。疫病を鎮めるために第51代・平成天皇は大極殿で名神に祈祷。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(2月24日)京都疾疫流行。疫病を鎮めるために第51代・平成天皇は大極殿で名神に祈祷。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(3月8日)京都疾疫流行。疫病を防ぐため、内裏・諸司左京職に読経させる。(『京都事典』) ▣(3月8日)京都疾疫流行。疫病を防ぐため、内裏・諸司左京職に読経させる。(『京都事典』) ▣ユ4月21日(3月22日)京都黄雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月21日(3月22日)京都黄雨。(『京都気象災害年表』) ▣(3月28日)京都黄雨。(『京都気象災害年表』) ▣(3月28日)京都黄雨。(『京都気象災害年表』) ▣(5月8日)京都疾疫流行。左右京病民を治療せしむ。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月8日)京都疾疫流行。左右京病民を治療せしむ。(『日本後紀』『日本災変通志』)  ▣(5月)前年より疾病流行。全国の飢饉・疫病により、租税の調免除。(『日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(5月)前年より疾病流行。全国の飢饉・疫病により、租税の調免除。(『日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(6月21日)葛野川の水防のため、有品親王・諸司把笏者に役夫を進めさせる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月21日)葛野川の水防のため、有品親王・諸司把笏者に役夫を進めさせる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(7月21日)葛野川の浚渫のため、内親王・命婦に役夫を進めさせる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(7月21日)葛野川の浚渫のため、内親王・命婦に役夫を進めさせる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月8日)左衛士坊の失火、民家180戸焼失。「物を賜ふこと差あり」(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(10月8日)左衛士坊の失火、民家180戸焼失。「物を賜ふこと差あり」(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(11月30日)右衛士の坊失火により78家焼失。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(11月30日)右衛士の坊失火により78家焼失。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣ユ12月27日(12月7日)京都大雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月27日(12月7日)京都大雷。(『京都気象災害年表』) ▣この年、疫病大流行、病死者多し。しばしば賑給。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣この年、疫病大流行、病死者多し。しばしば賑給。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) 
■809年(大同4年) ▣ユ7月8日(5月22日)京都霖雨。京中人民に賑給。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(5月25日)松尾、加茂社などに晴を祈る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月25日)松尾、加茂社などに晴を祈る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5-8月)京都霖雨。 ▣(5-8月)京都霖雨。 ▣ユ8月17日(7月3日)京都大旱。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月17日(7月3日)京都大旱。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月2日(7月19日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月2日(7月19日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣(8-9月)京都暴風。 ▣(8-9月)京都暴風。 ▣ユ9月17日(8月5日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月17日(8月5日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣(9月3日)旱疫に民疲れ、諸国脚夫を京下に役するのを停む。(『類聚国史』『日本災変通志』『疫病の古代史』) ▣(9月3日)旱疫に民疲れ、諸国脚夫を京下に役するのを停む。(『類聚国史』『日本災変通志』『疫病の古代史』)  ▣ユ10月17日(9月5日)京都暴風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月17日(9月5日)京都暴風。(『京都気象災害年表』)
■810年(大同5年/弘仁元年) ▣(1月7日)左京飢う、賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(9月23日)近年に水害・干害・疾病が相次ぎ出挙(すいこ、利子付貸付け制度)利息を5割から3割に軽減。(『類聚三代格』『疫病の古代史』) ▣(9月23日)近年に水害・干害・疾病が相次ぎ出挙(すいこ、利子付貸付け制度)利息を5割から3割に軽減。(『類聚三代格』『疫病の古代史』)  
■811年(弘仁2年) ▣(5月)疾病・旱により賑給実施。(『日本後紀』『疫病の古代史』)   ▣ユ10月2日(9月12日)京都大風。京中の盧舎破る。翌日、風損者に米給す。(『日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ10月2日(9月12日)京都大風。京中の盧舎破る。翌日、風損者に米給す。(『日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) 
■812年(弘仁3年) ▣ユ5月12日(3月28日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣(5月18日)京中飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月18日)京中飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日)京中、米価格高く、減価し貧民に売る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日)京中、米価格高く、減価し貧民に売る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月16日)京中米価騰貴のため、官倉米を出し減価。飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月16日)京中米価騰貴のため、官倉米を出し減価。飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)
■813年(弘仁4年) ▣(2月16日)山埼津頭で失火、延焼31家に米綿給する。(『日本紀略』『日本災変通志』)  ▣(6月1日)京畿内で病人・餓死者の路頭放置は禁じられる。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『疫病の古代史』『日本史総合年表』) ▣(6月1日)京畿内で病人・餓死者の路頭放置は禁じられる。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『疫病の古代史』『日本史総合年表』)
■814年(弘仁5年) ▣(6月3日) 京中飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月)京都疾疫流行。大同以来の「疾疫間発(連鎖)」。(『日本後紀』) ▣(7月)京都疾疫流行。大同以来の「疾疫間発(連鎖)」。(『日本後紀』) ▣ユ11月19日(10月4日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ11月19日(10月4日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月2日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月2日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣畿内・丹波・近江などで旱魃。 ▣畿内・丹波・近江などで旱魃。 ▣京都疾疫流行。疱瘡の再流行。(『類聚符宣抄』巻三) ▣京都疾疫流行。疱瘡の再流行。(『類聚符宣抄』巻三)
■815年(弘仁6年) ▣ユ7月25日(6月16日)近畿水害。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月2日(6月24日)山城大雷風。乙訓郡物集・国背で雷風、百姓盧舎壊す。震(雷)死す。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣ユ8月2日(6月24日)山城大雷風。乙訓郡物集・国背で雷風、百姓盧舎壊す。震(雷)死す。(『日本後紀』『日本災変通志』)  ▣(7月)京都洪水。 ▣(7月)京都洪水。 ▣(7月25日)水害により左右京畿内の田祖を免じる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(7月25日)水害により左右京畿内の田祖を免じる。(『日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(8月3日) 霖雨晴れず加茂社・伊勢太神宮に奉幣せしめる。(『日本後紀』『日本災変通志』) ▣(8月3日) 霖雨晴れず加茂社・伊勢太神宮に奉幣せしめる。(『日本後紀』『日本災変通志』)
■816年(弘仁7年) ▣ユ2月26日(1月25日)京都降沙。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月11日・グ9月15日(8月16日)京都・近畿大風、夜。羅城門倒す。京中・諸国被害多し。(『日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』) ▣この年、京都大旱。(『京都気象災害年表』) ▣この年、京都大旱。(『京都気象災害年表』)
■817年(弘仁8年) ▣翌年ユ1月5日(11月25日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■818年(弘仁9年) ▣ユ5月11日(4月3日)京都旱災。(『京都気象災害年表』) ▣(4月23日)広隆寺(太秦公寺)堂塔全焼亡。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』) ▣(4月23日)広隆寺(太秦公寺)堂塔全焼亡。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』) ⋄左右京職に命じ、行路の死者を埋葬させる。貧困者に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ⋄左右京職に命じ、行路の死者を埋葬させる。貧困者に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(7月24日)貴布禰などに祈雨。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(7月24日)貴布禰などに祈雨。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(10月9日)貴布禰などに祈雨、験あり。(『日本災変通志』) ▣(10月9日)貴布禰などに祈雨、験あり。(『日本災変通志』) ▣この年、大疫。(『古今著聞集』巻二、『平安京の災害史』) ▣この年、大疫。(『古今著聞集』巻二、『平安京の災害史』)
■819年(弘仁10年) ▣(3月2日)山城など飢う。勅に「倉貯既に尽きて賑贍するに物無く、宜しく貸借加え以てその急を救うべし」(『類聚国史』『日本災変通志』) ▣(5月17日)。貴布禰社に奉幣祈雨。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月17日)。貴布禰社に奉幣祈雨。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月9日)。霖雨止めるため貴布禰神・丹生川上神に白馬献じ奉幣し祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月9日)。霖雨止めるため貴布禰神・丹生川上神に白馬献じ奉幣し祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日)京中窮乏者に銭給す。(『日本紀略』) ▣(6月4日)京中窮乏者に銭給す。(『日本紀略』) ▣ユ8月14日(7月20日)京都大風雨。京中に白竜現れ暴風雨、民屋損ず。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ8月14日(7月20日)京都大風雨。京中に白竜現れ暴風雨、民屋損ず。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(7月28日)霖雨止め晴れることを貴布禰に祈る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月28日)霖雨止め晴れることを貴布禰に祈る。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月)京都・諸国大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(7月)京都・諸国大旱。(『京都気象災害年表』)
■820年(弘仁11年) ▣(3月5日)京中飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月4日)国郡司に命じ行路病者を収容・治療させる。(『類聚三代格』) ▣(5月4日)国郡司に命じ行路病者を収容・治療させる。(『類聚三代格』)
■821年(弘仁14年) ▣(6月5日)貴布禰神、丹生川上雨師神 に晴れることを祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(10月24日)河内大水に相接の山城・摂津にも水に瀕する百姓・資産漂失者あり、租税免じ貧窮者に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』) ▣(10月24日)河内大水に相接の山城・摂津にも水に瀕する百姓・資産漂失者あり、租税免じ貧窮者に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』) 
■822年(弘仁13年) ▣(1月26日)近年の災害頻発により京下の役廃止。(『類聚三代格』『疫病の古代史』) ▣(6月-9月)京都大旱。 ▣ユ7月26日(7月5日)近畿諸国祈雨。京都旱。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月26日(7月5日)近畿諸国祈雨。京都旱。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) (7月5日)山城国飢う。賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』) (7月5日)山城国飢う。賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』)
■823年(弘仁14年) ▣(2月1日)左右京飢民に銭賜う。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(2月)「天下大疫」。(『類聚国史』) ▣(2月)「天下大疫」。(『類聚国史』) ▣(3月16日)第53代・ 淳和天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ⋄京師米騰貴し、人民皆飢亡、穀倉院の穀1000斛を放出
、減価で貧民に売り与える。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月16日)第53代・ 淳和天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ⋄京師米騰貴し、人民皆飢亡、穀倉院の穀1000斛を放出
、減価で貧民に売り与える。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月22日)左右京飢う。穀倉院の穀出し賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月22日)左右京飢う。穀倉院の穀出し賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月18日)左右京病民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月18日)左右京病民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月1日)霖雨止めるため貴布禰社に奉幣祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月1日)霖雨止めるため貴布禰社に奉幣祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日-7月17日)貴布禰・乙訓などに奉幣祈雨。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日-7月17日)貴布禰・乙訓などに奉幣祈雨。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(10月7日)内裏火災。延政門北掖より失火。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月7日)内裏火災。延政門北掖より失火。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月21日)大蔵14間長殿失火。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月21日)大蔵14間長殿失火。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(10月24日)京中窮乏者を賑恤(賑給)。(『類聚国史』『日本紀略』) ▣(10月24日)京中窮乏者を賑恤(賑給)。(『類聚国史』『日本紀略』) ▣(11月22日)大蔵省焼亡。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月22日)大蔵省焼亡。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣翌年ユ1月10日(12月6日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月10日(12月6日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月14日)右京飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月14日)右京飢民に賑給。(『日本紀略』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣この年、諸国疫気流行し、百姓窮乏、詔、左右京・五畿内諸国に賑給。 (『日本紀略』『日本災変通志』) ▣この年、諸国疫気流行し、百姓窮乏、詔、左右京・五畿内諸国に賑給。 (『日本紀略』『日本災変通志』) 
■824年-834年(天長年間) ▣神泉苑でしばしば雨乞祈願、苑内に善女竜王が祀られ霊域化する。(『燈心草庵所蔵文書』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)
■824年(弘仁15年/天長元年) ▣ユ3月10日(2月7日)京都日曇・春、諸国大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(6月19日)鴨河(かもがわ)の堤防修補のために防鴨河使(ぼうかし)、防葛野河使(ぼうかどのかわし)を置く。任期は3年。(『類聚三代格』)。平安京に置かれた臨時の職。その設置は824年以前/弘仁年間(810-824)とも。 ▣(6月19日)鴨河(かもがわ)の堤防修補のために防鴨河使(ぼうかし)、防葛野河使(ぼうかどのかわし)を置く。任期は3年。(『類聚三代格』)。平安京に置かれた臨時の職。その設置は824年以前/弘仁年間(810-824)とも。 ▣(6月27日)京兆飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月27日)京兆飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣第53代・淳和天皇の勅命により、東寺の空海は神泉苑の池畔で雨乞いの法会(請雨経法)を行なったとの伝承。西寺の守敏との争い。(『明匠略伝』『東寺長者補任』『日本災変通志』) ▣第53代・淳和天皇の勅命により、東寺の空海は神泉苑の池畔で雨乞いの法会(請雨経法)を行なったとの伝承。西寺の守敏との争い。(『明匠略伝』『東寺長者補任』『日本災変通志』)
■825年(天長2年) ▣諸国、疫癘止まず。(『類聚国史』『疫病の古代史』)
■826年(天長3年) ▣(1月3日)左兵衛府厨院失火、厮女1人焼死。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(5月23日)左右京飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(5月23日)左右京飢民に賑給。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(8月27日)左右京飢民・病人・水害被害者に賑給。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月27日)左右京飢民・病人・水害被害者に賑給。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(8月)京都で疫病流行。 ▣(8月)京都で疫病流行。 ▣京都洪水。 ▣京都洪水。
■827年(天長4年) ▣ユ8月7日・グ8月11日(7月12日)京都地震。官舎・家屋全壊多数。M6.5-7.0/6.8。余震が翌828年(6月)まで続く。京都周辺の活断層(『類聚国史』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本被害地震総覧』「 地震インフォ」) 地震インフォ」) ▣ユ9月15日(8月21日)京都大風。屋宇顛覆。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月15日(8月21日)京都大風。屋宇顛覆。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)
■828年(天長5年) ▣ユ7月8日(5月23日)京都大雨洪水。京中道路氾濫、川決し山崩れ、人畜漂没、左右京に賑給。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)   ▣ユ8月7日(6月23日)京都大雷雨。害を防ぐため、野寺で僧30人に大般若経を読経させる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』) ▣ユ8月7日(6月23日)京都大雷雨。害を防ぐため、野寺で僧30人に大般若経を読経させる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』)  ▣(8月24日)水害のため北山神を祀る。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(8月24日)水害のため北山神を祀る。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)
■829年(天長6年) ▣(6月3日)姧盗(悪質な窃盗)絶滅のため京職に絶戸田を授けることを停める。(『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』)
 ▣(8月27日)霖雨を停めるため貴布禰などに奉幣、白毛ノ馬献じる。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(8月27日)霖雨を停めるため貴布禰などに奉幣、白毛ノ馬献じる。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣諸国、疫癘間発。百姓夭死。法華経か最勝王経の暗唱を指示。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣諸国、疫癘間発。百姓夭死。法華経か最勝王経の暗唱を指示。(『類聚国史』『疫病の古代史』)
■830年(天長7年) ▣(5月6日)諸国の地震・疫癘の災を除くため大極殿で百僧が大般若経輪読。(『類聚国史』『日本災変通志』)  ▣(7月16日)内裏西北角御曹司に落雷。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月16日)内裏西北角御曹司に落雷。(『日本紀略』『日本災変通志』)
■831年(天長8年) ▣(5月25日)京中の飢病百姓に賑給。 (『日本紀略』『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(12月9日)防鴨河所(使)・防葛野河所(使)の別当任期が3年から4年に改められる。(『類聚三代格』巻五、「太政官符」『平安京の災害史』)
▣(閏12月)内裏に「物怪(もののけ)」あり、第50代・桓武天皇の柏原山陵に使者遣わされる。(『日本紀略』) ▣(12月9日)防鴨河所(使)・防葛野河所(使)の別当任期が3年から4年に改められる。(『類聚三代格』巻五、「太政官符」『平安京の災害史』)
▣(閏12月)内裏に「物怪(もののけ)」あり、第50代・桓武天皇の柏原山陵に使者遣わされる。(『日本紀略』)
■832年(天長9年) ▣(5月27日)京都疾疫流行。左右京の病者に賑給。(『日本紀略』『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣夏 畿内炎旱。 ▣夏 畿内炎旱。
■833年(天長10年) ▣(2月28日)第54代・仁明天皇践祚。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(5月28日)京師・五畿内など皆飢疫、賑給。(『続日本後紀』)  ⋄左右京の京戸に、東西堀川杭料、檜材1万5000株出させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月)「疫癘間発(連鎖)」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ⋄左右京の京戸に、東西堀川杭料、檜材1万5000株出させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月)「疫癘間発(連鎖)」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣(7月28日)霖雨旬に亘り止まず、松尾・賀茂・貴布禰などに奉幣し晴を祈る。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月28日)霖雨旬に亘り止まず、松尾・賀茂・貴布禰などに奉幣し晴を祈る。(『続日本後紀』『日本災変通志』)
■834年(天長11年/承和元年) ▣(4月26日)京都疾疫流行。疫癘頻発し、病苦多し、京師の諸寺に祈らしめ疫気を攘う。(『続日本後紀』『日本災変通志』『疫病の古代史』) ▣(6月30日)甘澍(雨)を祈り、風災を防ぎぐため大極殿で3日間大般若経転読。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月30日)甘澍(雨)を祈り、風災を防ぎぐため大極殿で3日間大般若経転読。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣ユ8月20日(7月12日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月20日(7月12日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月27日(8月21日)京都暴風大雨。民屋壊す。諸名神に風雨止めんことを祈る。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月27日(8月21日)京都暴風大雨。民屋壊す。諸名神に風雨止めんことを祈る。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣(8月22日)京中風雨、民家往々倒壊。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(8月22日)京中風雨、民家往々倒壊。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) 
■835年(承和2年) ▣(4月)「諸国疫癘流行」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣(10月26日)京師雷電甚し。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(10月26日)京師雷電甚し。(『続日本後紀』『日本災変通志』)
■836年(承和3年) ▣ユ6月5日(5月18日)京都大風暴雨。夜。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣(5月24日)京都疾疫流行。左右京の病民に賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(5月24日)京都疾疫流行。左右京の病民に賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)   ▣ユ7月1日(閏5月14日)京都颷風(つむじかぜ)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月1日(閏5月14日)京都颷風(つむじかぜ)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月5日(7月21日)京都大雷雨。殊に切なり。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月5日(7月21日)京都大雷雨。殊に切なり。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣(7月)「諸国疫癘間発(連鎖)」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣(7月)「諸国疫癘間発(連鎖)」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣この年、僧・道昌、大堰川の修復をする。(『弘法大師弟子伝』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣この年、僧・道昌、大堰川の修復をする。(『弘法大師弟子伝』『京都の歴史10 年表・事典』)
■837年(承和4年) ▣(6月)「疫癘間発(連鎖)」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣(10月1日)左右京の飢民・病人に賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月1日)左右京の飢民・病人に賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(11月11日)京都大風、京中屋舎往々破壊。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(11月11日)京都大風、京中屋舎往々破壊。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(12月2日)盗人、春興殿に入り、絹50余疋盗む。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月2日)盗人、春興殿に入り、絹50余疋盗む。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(12月5日)女盗2人、清涼殿に入る。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月5日)女盗2人、清涼殿に入る。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣翌年ユ1月10日(12月11日)京都大風。京中の屋舎多く倒れる。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣翌年ユ1月10日(12月11日)京都大風。京中の屋舎多く倒れる。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(12月21日)盗人、大蔵省東長殿に入り、絁布など多く盗む。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月21日)盗人、大蔵省東長殿に入り、絁布など多く盗む。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(12月22日)この日以前に、盗賊、春興殿・清涼殿に侵入し、六衛府に京中捜索させる。(『続日本後紀』『日本史総合年表』) ▣(12月22日)この日以前に、盗賊、春興殿・清涼殿に侵入し、六衛府に京中捜索させる。(『続日本後紀』『日本史総合年表』) 
■838年(承和5年) ▣(2月12日)畿内諸国に群盗横行、左右衛門の府生・看督などを遣わして逮捕させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』)  ▣(4月)「疫癘間発(連鎖)」(『日本紀略』『疫病の古代史』) ▣(4月)「疫癘間発(連鎖)」(『日本紀略』『疫病の古代史』) ▣ユ6月15日(5月20日)京都水害。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月15日(5月20日)京都水害。(『京都気象災害年表』) ▣(5月25日)山城国飢う、近江国正税穀で賑給。(『日本災変通志』) ▣(5月25日)山城国飢う、近江国正税穀で賑給。(『日本災変通志』) ▣ユ9月12日(8月20日)京都大風・暴風雨。民家多く倒れる。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ9月12日(8月20日)京都大風・暴風雨。民家多く倒れる。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』)   ▣(8月28日)大雨により上賀茂・下鴨・松尾・乙訓など諸社に奉幣する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(8月28日)大雨により上賀茂・下鴨・松尾・乙訓など諸社に奉幣する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)
■839年(承和6年) ▣(閏1月)「諸国疫疫」。(『類聚国史』『疫病の古代史』) ▣(閏1月5日)綾部司織手町失火、百姓盧舎数烟を焼く。(『続日本後紀』『京都事典』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(閏1月5日)綾部司織手町失火、百姓盧舎数烟を焼く。(『続日本後紀』『京都事典』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月29日)祈雨のため貴布禰・丹生川上雨師神に奉幣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月29日)祈雨のため貴布禰・丹生川上雨師神に奉幣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(4月15日)左馬寮国飼町失火。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月15日)左馬寮国飼町失火。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月17日)炎旱。春より降雨なく、松尾・上賀茂・下鴨・貴船など諸社に奉幣、15大寺、高山有験寺に仁王経を転読させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月17日)炎旱。春より降雨なく、松尾・上賀茂・下鴨・貴船など諸社に奉幣、15大寺、高山有験寺に仁王経を転読させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月20日-21日)雨乞使者を七道諸国名神、宇治・綴喜などの社に派遣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(4月20日-21日)雨乞使者を七道諸国名神、宇治・綴喜などの社に派遣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月1日)祈雨のため丹生・貴布禰に使い遣る。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月1日)祈雨のため丹生・貴布禰に使い遣る。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月6日)東西市人、朱雀大路で雨乞する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(6月6日)東西市人、朱雀大路で雨乞する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)
■840年(承和7年) ▣(2月12日)京城に群盗多発、六衛府に夜警行わせる。(『続日本後紀』『日本史総合年表』『京都の歴史10 年表・事典』)
 ▣(2月24日)勅により京中の高齢者・飢病百姓を賑恤。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(2月24日)勅により京中の高齢者・飢病百姓を賑恤。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月6日)京中に六衛府を遣わし盗賊捜索させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月6日)京中に六衛府を遣わし盗賊捜索させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(4月29日)勅、炎旱続き嘉苗枯れ、松尾・賀茂・乙訓・貴布禰などに奉幣祈雨・防風災祈願。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月29日)勅、炎旱続き嘉苗枯れ、松尾・賀茂・乙訓・貴布禰などに奉幣祈雨・防風災祈願。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(5月15日)祈雨のため、上賀茂社・下鴨社・松尾社・伊勢神宮などに奉幣。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(5月15日)祈雨のため、上賀茂社・下鴨社・松尾社・伊勢神宮などに奉幣。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(5月20日)京中の飢病者に飯・米・銭を賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月20日)京中の飢病者に飯・米・銭を賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月9日)勅、陰雨降らず、貴布禰・丹生などに祈雨せしむ。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月9日)勅、陰雨降らず、貴布禰・丹生などに祈雨せしむ。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(6月)「疫癘間発(連鎖)」。(『続日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(6月)「疫癘間発(連鎖)」。(『続日本後紀』『疫病の古代史』)
■841年(承和8年) ▣(4月29日)祈雨のため松尾社・賀茂社・乙訓社・貴布禰社などに奉幣。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)
 ▣(5月)「疫癘間発(連鎖)」。(『続日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(5月)「疫癘間発(連鎖)」。(『続日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(7月6日)左兵衛府駕輿丁西北角より失火、百姓30余戸焼く。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(7月6日)左兵衛府駕輿丁西北角より失火、百姓30余戸焼く。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣ユ8月5日(7月15日)京都落雷降雹。雷が大極殿東楼南角の柱に震す(落雷)。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月5日(7月15日)京都落雷降雹。雷が大極殿東楼南角の柱に震す(落雷)。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月18日(8月30日)京都大雨洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月18日(8月30日)京都大雨洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(9月1日)京中大洪水、百姓屋舎漂流、京中橋、山崎橋など尽く断絶。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(9月1日)京中大洪水、百姓屋舎漂流、京中橋、山崎橋など尽く断絶。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)
■842年(承和9年) ▣(3月15日)貴布禰などに幣を頒ち、甘雨あらんことを祈る。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月22日)祈雨のため松尾、鴨御祖、鴨別雷、乙訓などの名神に奉幣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月22日)祈雨のため松尾、鴨御祖、鴨別雷、乙訓などの名神に奉幣。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月)春雨少なく旱多い。(『類聚三代格』『続日本後紀』) ▣(3月)春雨少なく旱多い。(『類聚三代格』『続日本後紀』) ▣(7月6日)貴布禰・乙訓・丹生川上神に奉幣祈雨。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月6日)貴布禰・乙訓・丹生川上神に奉幣祈雨。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月17日)「承和の変」伴岑健・橘逸勢ら叛する。京職に命じ左右京・宇治橋・大原道・大枝道・山崎橋・淀橋など固める。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(7月17日)「承和の変」伴岑健・橘逸勢ら叛する。京職に命じ左右京・宇治橋・大原道・大枝道・山崎橋・淀橋など固める。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(7月18日/19日) 左京工町火災、民屋20戸焼く。罹災百姓に6万銭班給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(7月18日/19日) 左京工町火災、民屋20戸焼く。罹災百姓に6万銭班給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(10月14日)第54代・仁明天皇は左右京職・東西悲田院に命じ、料物を給し嶋田・鴨河原などで髑髏5500余を焼かせ(焼斂)埋葬させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(10月23日)太政官は義倉の物を悲田に充て鴨川の髑髏を集め葬らせる。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(10月14日)第54代・仁明天皇は左右京職・東西悲田院に命じ、料物を給し嶋田・鴨河原などで髑髏5500余を焼かせ(焼斂)埋葬させる。(『続日本後紀』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(10月23日)太政官は義倉の物を悲田に充て鴨川の髑髏を集め葬らせる。(『続日本後紀』『日本災変通志』)
■843年(承和10年) ▣(1月8日)勅「疫癘間発(連鎖)」。(『続日本後紀』『疫病の古代史』) ▣(3月25日)義倉の品で東西悲田院の病者・貧窮者に賑給する。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月25日)義倉の品で東西悲田院の病者・貧窮者に賑給する。(『続日本後紀』『日本災変通志』)  ▣(6月25日) 丹後など18国飢う。勅して賑恤。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月25日) 丹後など18国飢う。勅して賑恤。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)
■844年(承和11年) ▣ユ1月23日(1月1日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(11月4日)王家家人・百姓らが鴨川を汚すことを禁じる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月4日)王家家人・百姓らが鴨川を汚すことを禁じる。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』)
■845年(承和12年) ▣ユ2月10日(1月1日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(3月29日)仁寿殿東廂火、撲滅。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(3月29日)仁寿殿東廂火、撲滅。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月1日)大極殿で大般若経転読祈雨、(6日)澍雨。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月1日)大極殿で大般若経転読祈雨、(6日)澍雨。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月4日)山城国飢う。賑給(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月4日)山城国飢う。賑給(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月9日) 綴喜・相楽郡で(3月)上旬より虻殊多く牛馬咬み病死。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(5月9日) 綴喜・相楽郡で(3月)上旬より虻殊多く牛馬咬み病死。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月4日)山城国飢う、賑給。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣(7月4日)山城国飢う、賑給。(『続日本後紀』『日本災変通志』) ▣ユ10月25日(9月21日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月25日(9月21日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣(11月14日)鴨河悲田院(三条北鴨川西岸)で養育した孤児18人に新生連の姓を賜う。左京に貫付する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』) ▣(11月14日)鴨河悲田院(三条北鴨川西岸)で養育した孤児18人に新生連の姓を賜う。左京に貫付する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)
■846年(承和13年) ▣(5月13日)八省院に3日間読経祈雨。(『続日本後紀』『日本災変通志』)
■847年(承和14年) ▣ユ1月21日(1月1日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(5月18日)雨止まず、左右京の飢民に賑給。 (『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月18日)雨止まず、左右京の飢民に賑給。 (『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ7月18日(6月3日)京都大風雨。平安京で大規模な暴風雨。(12日)滝のような降雨。(21日)霖雨やむ。(『続日本後記』『京都気象災害年表』) ▣ユ7月18日(6月3日)京都大風雨。平安京で大規模な暴風雨。(12日)滝のような降雨。(21日)霖雨やむ。(『続日本後記』『京都気象災害年表』)  ▣(8月21日)京都大火。西京衛士町失火、百姓盧舎30余戸焼く。(『続日本後記』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(8月21日)京都大火。西京衛士町失火、百姓盧舎30余戸焼く。(『続日本後記』『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』)
■848年(承和15年/嘉祥元年) ▣(3月5日)作物所冶師の失火により、永安門西廊少し火災。(『続日本後記』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月6日)神泉苑の東垣瓦8丈余頽れ落ちる。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣(3月6日)神泉苑の東垣瓦8丈余頽れ落ちる。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣(6月28日)右衛門府南町失火、民家数10戸焼く。(『続日本後記』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(6月28日)右衛門府南町失火、民家数10戸焼く。(『続日本後記』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(7月2日)松尾・上下賀茂社・貴布禰などに奉幣祈雨。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣(7月2日)松尾・上下賀茂社・貴布禰などに奉幣祈雨。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣(7月6日)祈雨のため八省院に大般若経転読。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣(7月6日)祈雨のため八省院に大般若経転読。(『続日本後記』『日本災変通志』) ▣ユ8月9日(7月7日)京都颷風。御所内に旋風風、被害あり。(『続日本後記』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月9日(7月7日)京都颷風。御所内に旋風風、被害あり。(『続日本後記』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月31日(7月29日)京都落雷。東西二京約11カ所、木工寮倉・東市司楼・弘文院・新王家など5家、ほか3処、小民宅多数。(『続日本後記』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月31日(7月29日)京都落雷。東西二京約11カ所、木工寮倉・東市司楼・弘文院・新王家など5家、ほか3処、小民宅多数。(『続日本後記』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月5日(8月5日)京都大雨洪水。(3日)より嘉祥畿内大洪水。(5日)宇治橋・河陽(かや)橋が損壊、茨田堤処々潰れる。人畜被害甚大。京中被害者に米・塩賑給。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣ユ9月5日(8月5日)京都大雨洪水。(3日)より嘉祥畿内大洪水。(5日)宇治橋・河陽(かや)橋が損壊、茨田堤処々潰れる。人畜被害甚大。京中被害者に米・塩賑給。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) 
■849年(嘉祥2年) ▣ユ5月5日(4月10日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣(5月-6月)畿内霖雨。 ▣(5月-6月)畿内霖雨。 ▣ユ6月24日(6月1日)畿内霜・雨・飢饉。霖雨害により、官倉を開いて飢民に賑給する。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ6月24日(6月1日)畿内霜・雨・飢饉。霖雨害により、官倉を開いて飢民に賑給する。(『続日本後紀』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)   ▣(10月23日)京中の飢民を賑恤。太皇太后・橘嘉智子、銭50万を京中棄民に賑給する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(10月23日)京中の飢民を賑恤。太皇太后・橘嘉智子、銭50万を京中棄民に賑給する。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(閏12月10日)第54代・仁明天皇、京中窮民に米銭賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(閏12月10日)第54代・仁明天皇、京中窮民に米銭賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』)
■850年(嘉祥3年) ▣(1月26日)左右京職・畿内国司に命じ、群盗捜捕。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)
 ▣(2月3日)六衛府官人、京中群盗捕う。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(2月3日)六衛府官人、京中群盗捕う。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月10日)京中貧民賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月10日)京中貧民賑給。(『続日本後紀』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月21日)第55代・文徳天皇践祚。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ5月12日(3月27日)京都大雷雨。暴風雷雨により嵯峨山陵で倒木。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(3月21日)第55代・文徳天皇践祚。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ5月12日(3月27日)京都大雷雨。暴風雷雨により嵯峨山陵で倒木。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)   ▣ユ5月15日(4月)京都冷寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月15日(4月)京都冷寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月15日(5月2日)京都大風、倒木被害。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ6月15日(5月2日)京都大風、倒木被害。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ6月24日(5月11日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月24日(5月11日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月9日(5月26日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月9日(5月26日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月15日(6月3日) 西寺落雷。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ6月15日(6月3日) 西寺落雷。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(7月2日) 左右京貧窮者に賑給。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(7月2日) 左右京貧窮者に賑給。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ9月3日(7月24日)京都大雨大水。大極殿前道12丈水潦、山崎橋断つ。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月3日(7月24日)京都大雨大水。大極殿前道12丈水潦、山崎橋断つ。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)
■851年(嘉祥4年/仁寿元年) ▣ユ6月10日(5月8日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣(5月9日)左右京の窮貧者に賑給、丹生川上神に幣・馬を奉り止雨の祈り。 (『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月9日)左右京の窮貧者に賑給、丹生川上神に幣・馬を奉り止雨の祈り。 (『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ7月5日(6月3日)京都雨水。晴れ祈願、賀茂・松尾・乙訓など。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月5日(6月3日)京都雨水。晴れ祈願、賀茂・松尾・乙訓など。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ9月8日(8月10日)京都大雨洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月8日(8月10日)京都大雨洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(8月15日)京師、水害を被害る者に賑給。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(8月15日)京師、水害を被害る者に賑給。(『文徳実録』『日本災変通志』)  ▣冬 暖冬。(『京都気象災害年表』) ▣冬 暖冬。(『京都気象災害年表』)
■852年(仁寿2年) ▣(3月6日)京師最貧者に賑給。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(7月10日)祈雨のため賀茂・松尾・稲荷・貴布禰などに奉幣。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(7月10日)祈雨のため賀茂・松尾・稲荷・貴布禰などに奉幣。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(7月28日) 京都暴風雨、禾稼(穀物)傷む。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(7月28日) 京都暴風雨、禾稼(穀物)傷む。(『文徳実録』『日本災変通志』)  ▣ユ9月28日(閏8月12日)京都大雨・洪水・大風。東堀川の水、冷泉院池中に流入。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ9月28日(閏8月12日)京都大雨・洪水・大風。東堀川の水、冷泉院池中に流入。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)  ▣(閏8月16日)京師で風害にあった者に廩院の米を賑給。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣(閏8月16日)京師で風害にあった者に廩院の米を賑給。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』)  ▣(閏8月27日)京都大雨(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(閏8月27日)京都大雨(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(閏8月29日)止雨のため賀茂・松尾などに奉幣祈願。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(閏8月29日)止雨のため賀茂・松尾などに奉幣祈願。(『文徳実録』『日本災変通志』)
■853年(仁寿3年) ▣(2月)京師・近畿外に天然痘(皰瘡、疱瘡)流行、死者多数。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』『日本史総合年表』) ▣(3月22日)災疫攘うため大極殿で名僧百口を請じ、大般若経を3日転読。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(3月22日)災疫攘うため大極殿で名僧百口を請じ、大般若経を3日転読。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(3月27日)穀倉院の米塩を疱瘡患者に賑給。(『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(3月27日)穀倉院の米塩を疱瘡患者に賑給。(『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)  ▣(4月25日)京都疾疫流行。疱瘡流行し人民疫死のため、賀茂祭中止(停止)になる。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月25日)京都疾疫流行。疱瘡流行し人民疫死のため、賀茂祭中止(停止)になる。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(4月26日)京都疾疫流行。天然痘流行、承和10年以前の未進調庸を免じ医薬を賜う。孫王が勝手に畿外に出ることを禁じる。(『文徳実録』『日本史総合年表』) ▣(4月26日)京都疾疫流行。天然痘流行、承和10年以前の未進調庸を免じ医薬を賜う。孫王が勝手に畿外に出ることを禁じる。(『文徳実録』『日本史総合年表』)
  ▣(4月)京都疾疫流行。疱瘡に罹り和気貞臣、成康親王が死亡。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(4月)京都疾疫流行。疱瘡に罹り和気貞臣、成康親王が死亡。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(5月5日)京都疾疫流行。災疫により騎射走馬の観覧停む。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(5月5日)京都疾疫流行。災疫により騎射走馬の観覧停む。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(8月1日)右京(西京)で失火、民家180余焼失。平安城民家大火の初めになる。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(8月1日)右京(西京)で失火、民家180余焼失。平安城民家大火の初めになる。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ10月6日(9月1日)京都大風。屋発ち木を抜く。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ10月6日(9月1日)京都大風。屋発ち木を抜く。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)
■854年(仁寿4年) ▣(2月20日)丹後の飢民に賑給。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月1日(3月)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月1日(3月)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月30日(5月)京都甚寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月30日(5月)京都甚寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月24日(7月27日)京都・美濃暴風・洪水氾濫。甚雨洪水。屋を発ち木を抜く。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月24日(7月27日)京都・美濃暴風・洪水氾濫。甚雨洪水。屋を発ち木を抜く。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) 
■855年(斉衡2年) ▣(1月22日)京師賊多く掠奪。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月7日(3月17日)京都大雨風。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ4月7日(3月17日)京都大雨風。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣(3月)左右馬寮の馬殆ど疫死。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(3月)左右馬寮の馬殆ど疫死。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月20日(4月)京都寒霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月20日(4月)京都寒霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月3日(閏4月15日)京都大雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月3日(閏4月15日)京都大雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月23日(6月6日)京都落雷。建礼門前。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月23日(6月6日)京都落雷。建礼門前。(『京都気象災害年表』) ▣(10月18日)山崎津頭で失火、民家300余戸焼失。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(10月18日)山崎津頭で失火、民家300余戸焼失。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』)
■856年(斉衡3年) ▣ユ4月11日(3月3日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月16日・グ4月20日(3月8日)京都で地震。(「 ▣ユ4月16日・グ4月20日(3月8日)京都で地震。(「 地震インフォ」) 地震インフォ」) ▣(3月)京都地震多い。京師、城南。М6.0-6.5 「是月、地數震、京師及城南屋舎毀壊」(『文徳実録』)。(『大日本史』『『京都の歴史10
年表・事典』日本被害地震総覧』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(3月)京都地震多い。京師、城南。М6.0-6.5 「是月、地數震、京師及城南屋舎毀壊」(『文徳実録』)。(『大日本史』『『京都の歴史10
年表・事典』日本被害地震総覧』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月9日)大極殿、冷然院、賀茂社、松尾社などで大般若経読誦3日間で災疫祓う。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月3日(5月28日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月3日(12月4日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(5月9日)大極殿、冷然院、賀茂社、松尾社などで大般若経読誦3日間で災疫祓う。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月3日(5月28日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月3日(12月4日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■857年(斉衡4年/天安元年) ▣(1月1日)近来処々の井泉涸れ左京三条-四条間被害尤も甚だしい。この日初めて降雨。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』『京都の歴史10
年表・事典』) ▣(3月16日・17日・25日)群盗賊を京南平城に追捕。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月16日・17日・25日)群盗賊を京南平城に追捕。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月16日)左右近衛・左右兵衛・検非違使・左右馬寮に、京南の群盗捕えさせる。(『文徳実録』『日本史総合年表』) ▣(3月16日)左右近衛・左右兵衛・検非違使・左右馬寮に、京南の群盗捕えさせる。(『文徳実録』『日本史総合年表』) ▣(5月20日)京都地震・雷雨。近来の大雨やまず、京都洪水。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月20日)京都地震・雷雨。近来の大雨やまず、京都洪水。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』)   ▣ユ6月24日(5月29日)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月24日(5月29日)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(8月14日)京都ひどい霧。(『文徳実録』) ▣(8月27日)右近衛舎人町失火。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月14日)京都ひどい霧。(『文徳実録』) ▣(8月27日)右近衛舎人町失火。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ9月19日(8月28日)京都旱。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月19日(8月28日)京都旱。(『京都気象災害年表』) ▣(8月-9月)京都旱魃。 ▣(8月-9月)京都旱魃。 ▣(10月23日)蔵殿に女盗入り捕われる。夜。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(10月23日)蔵殿に女盗入り捕われる。夜。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ11月19日(10月29日)京都雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ11月19日(10月29日)京都雪。(『京都気象災害年表』) ▣この年、京都洪水・雷雨・地震被害多い。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣この年、京都洪水・雷雨・地震被害多い。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  
■858年(天安2年) ▣(1月27日)常住寺西南別院焼亡。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ2月15日(1月28日)京都暴風大雨。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ2月15日(1月28日)京都暴風大雨。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣ユ2月28日(2月11日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ2月28日(2月11日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(2月22日)馬寮官人・近衛ら、京中盗賊を捜捕。(『文徳実録』) ▣(2月22日)馬寮官人・近衛ら、京中盗賊を捜捕。(『文徳実録』)  ▣(4月9日)宝皇寺(鳥戸寺)金堂・礼堂焼亡。(『文徳実録』『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(4月9日)宝皇寺(鳥戸寺)金堂・礼堂焼亡。(『文徳実録』『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣ユ3月31日(閏2月13日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ3月31日(閏2月13日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月14日(3月28日)京都雲なく雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月14日(3月28日)京都雲なく雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月22日(4月6日)京都雷・雨・雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月22日(4月6日)京都雷・雨・雹。(『京都気象災害年表』)   ▣(4月24日)大舎人寮焼亡。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(4月24日)大舎人寮焼亡。(『文徳実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(5月15日)陰雨止まず、洪水汎溢、京の東西に両河、人馬通ぜず。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(5月15日)陰雨止まず、洪水汎溢、京の東西に両河、人馬通ぜず。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月6日(5月22日)京都大雨洪水。東堀川・大宮川・鴨川氾濫、橋梁断絶。死者多数。大雨により東堀川の水、冷然院に浸水し、左衛門陣宿直小屋浮き流れる。左右京の水害甚だしい。流死者衆(おお)し。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣ユ7月6日(5月22日)京都大雨洪水。東堀川・大宮川・鴨川氾濫、橋梁断絶。死者多数。大雨により東堀川の水、冷然院に浸水し、左衛門陣宿直小屋浮き流れる。左右京の水害甚だしい。流死者衆(おお)し。(『文徳実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣ユ7月10日(5月26日)京都雲なく雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月10日(5月26日)京都雲なく雹。(『京都気象災害年表』) ▣(5月27日)勅使を遣し、両京洪水害を巡検させる。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(5月27日)勅使を遣し、両京洪水害を巡検させる。(『文徳実録』『日本災変通志』) ▣(5月29日)水害被災の左右京窮民に、穀倉院の穀2000石・民部省廩院の米500石・大膳職の塩25石を賑給。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月29日)水害被災の左右京窮民に、穀倉院の穀2000石・民部省廩院の米500石・大膳職の塩25石を賑給。(『文徳実録』『京都事典』『日本災変通志』)  ▣ユ8月3日(6月21日)京都大風・濃霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月3日(6月21日)京都大風・濃霧。(『京都気象災害年表』) ▣(8月27日)第56代・清和天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月27日)第56代・清和天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)
■859年(天安3年/貞観元年) ▣(2月5日)右京失火、民家数10戸焼く。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ5月6日(4月1日)京都落雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月6日(4月1日)京都落雷。(『京都気象災害年表』) ▣(4月24日)京都大雨。夜、賀茂神祭で雨水流奔し渉り難し。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(4月24日)京都大雨。夜、賀茂神祭で雨水流奔し渉り難し。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ6月21日(5月17日)京都雷・雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月21日(5月17日)京都雷・雹。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ7月4日(6月1日)京都霖雨大水・大雨水。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月4日(6月1日)京都霖雨大水・大雨水。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(6月4日)大雨による京邑の飢乏者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月4日)大雨による京邑の飢乏者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ7月25日(6月22日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月25日(6月22日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ8月20日(7月19日)京都雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月20日(7月19日)京都雷雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ9月12日(8月12日)京都大風雨。京師、大雨風、人居で風に壊されるもの多し。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ9月12日(8月12日)京都大風雨。京師、大雨風、人居で風に壊されるもの多し。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(9月4日)霖雨止めるため使いを遣り賀茂御祖・別雷・貴布祢・乙訓・稲荷などに奉幣祈願。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(9月4日)霖雨止めるため使いを遣り賀茂御祖・別雷・貴布祢・乙訓・稲荷などに奉幣祈願。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(9月8日)風雨の祈のため山城国六社・大和国二十九社などに使いを遣り奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(9月8日)風雨の祈のため山城国六社・大和国二十九社などに使いを遣り奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』)  ▣ユ10月8日(9月9日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月8日(9月9日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ12月20日(11月23日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月20日(11月23日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■860年(貞観2年) ▣ユ4月30日(4月6日)京都霜害。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月5日(4月11日)京都廻飄(つむじ風)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月5日(4月11日)京都廻飄(つむじ風)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月28日(5月5日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月28日(5月5日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月10日(5月18日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月10日(5月18日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月25日(6月3日)京都大水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月25日(6月3日)京都大水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月11日(7月21日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月11日(7月21日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣(8月27日)盗人、神祇官西院斎戸神殿に入り、衣など奪う。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月27日)盗人、神祇官西院斎戸神殿に入り、衣など奪う。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ9月18日(8月30日)京都大水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月18日(8月30日)京都大水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月2日-3日(9月14日-15日/14日/15日)京都大風。平安京・畿内風水害、京都・近畿地方に台風襲来、風雨止まず。都城の東西両河の桂川・鴨川洪水。人馬通ぜず。樹折り屋発く。京師の盧舎破損する者甚だ多し。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本の自然災害』) ▣ユ10月2日-3日(9月14日-15日/14日/15日)京都大風。平安京・畿内風水害、京都・近畿地方に台風襲来、風雨止まず。都城の東西両河の桂川・鴨川洪水。人馬通ぜず。樹折り屋発く。京師の盧舎破損する者甚だ多し。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本の自然災害』)  ▣翌ユ年1月2日(11月17日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣翌ユ年1月2日(11月17日)京都大風。(『京都気象災害年表』)
■861年(貞観3年) ▣(3月13日)防鴨河使・防葛野河使が廃され、業務は山城国司に移る。その後もたびたび復活。(『三代実録』『類聚三代格』巻一六、『京都の歴史10
年表・事典』『日本史総合年表』『平安京の災害史』) ▣(5月15日)祈雨のため京都に近い明神七社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月15日)祈雨のため京都に近い明神七社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月14日(6月3日)京都雲なく雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月14日(6月3日)京都雲なく雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月2日(6月22日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月20日(7月11日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月2日(6月22日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月20日(7月11日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣(8月)京都赤痢流行。10歳以下の男女児多数死亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『疫病の古代史』『平安京の災害史』) ▣(8月)京都赤痢流行。10歳以下の男女児多数死亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『疫病の古代史』『平安京の災害史』) ▣昨年(9月)の桂川洪水に際し、東寺領山城国・上桂荘で破堤により、洪水被害を一カ所(遊水地)に集中させる。その後、荒野と化すため「悪行の第一なり」と批判。(「山城国上桂庄史料」『災害と生きる中世』) ▣昨年(9月)の桂川洪水に際し、東寺領山城国・上桂荘で破堤により、洪水被害を一カ所(遊水地)に集中させる。その後、荒野と化すため「悪行の第一なり」と批判。(「山城国上桂庄史料」『災害と生きる中世』)
■862年(貞観4年) ▣(3月8日)左右京職に命じ、朱雀大路各坊門を兵士に守らせる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)
 ▣(3月15日)親王・公卿などの家司・別当などを保長とし京中守らせる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』) ▣(3月15日)親王・公卿などの家司・別当などを保長とし京中守らせる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)  ▣ユ4月21日(3月19日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月21日(3月19日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月4日(4月2日)京都大雨水・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月4日(4月2日)京都大雨水・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(5月16日)左京右衛門府衛士居住区失火。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月16日)左京右衛門府衛士居住区失火。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月-7月)京都霖雨。 ▣(5月-7月)京都霖雨。 ▣ユ7月18日(6月18日)京都霖雨・賑給。(5月)以来大雨やまず京中飢饉、賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ7月18日(6月18日)京都霖雨・賑給。(5月)以来大雨やまず京中飢饉、賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)  ▣ユ9月28日(9月/9月17日)京都大旱。人家の井水涸れ、神泉苑西北門を開き水を汲ませる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣ユ9月28日(9月/9月17日)京都大旱。人家の井水涸れ、神泉苑西北門を開き水を汲ませる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣秋より数カ月 京都地震頻発。(『三代実録』『京都事典』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣秋より数カ月 京都地震頻発。(『三代実録』『京都事典』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣冬末-翌年(1月末) 京畿内外に咳病(咳逆病)流行。死者甚だ多く、京師飢病者に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』) ▣冬末-翌年(1月末) 京畿内外に咳病(咳逆病)流行。死者甚だ多く、京師飢病者に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』) 
■863年(貞観5年) ▣昨年冬末-(1月末)京畿内外に咳病(咳逆病)流行。死者甚だ多く、京師飢病者に賑給。(『類聚国史』『日本災変通志』)  ▣(1月27日)京畿・畿外に咳逆病(咳嗽、流行性感冒?)流行し、死者多数。京師の飢病者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』) ▣(1月27日)京畿・畿外に咳逆病(咳嗽、流行性感冒?)流行し、死者多数。京師の飢病者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』)  ▣ユ3月7日(2月14日)京都大風。民屋壊す。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ3月7日(2月14日)京都大風。民屋壊す。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(3月4日)疫病終息により、諸国名神に報賽の幣帛捧げる。(『三代実録』『平安京の災害史』) ▣(3月4日)疫病終息により、諸国名神に報賽の幣帛捧げる。(『三代実録』『平安京の災害史』) ▣ユ5月2日(4月11日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月2日(4月11日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣(4月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(4月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月28日(5月7日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月28日(5月7日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣(5月20日)朝廷により神泉苑に藤原基経ら遣わし御霊会を行い、崇道天皇(早良親王)・伊予親王ら6人を祀る。僧に金光明経・般若心経を読誦させ、良家の子弟ら歌舞披露、苑門開き公開する。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』『日本史総合年表』) ▣(5月)近代以来、疫病繁発。(『三代実録』『平安京の災害史』) ▣(5月20日)朝廷により神泉苑に藤原基経ら遣わし御霊会を行い、崇道天皇(早良親王)・伊予親王ら6人を祀る。僧に金光明経・般若心経を読誦させ、良家の子弟ら歌舞披露、苑門開き公開する。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『平安京の災害史』『日本史総合年表』) ▣(5月)近代以来、疫病繁発。(『三代実録』『平安京の災害史』) ▣(6月21日)京師飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(6月21日)京師飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣ユ6月20日(6月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月20日(6月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月7日(7月21日)京都大雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月7日(7月21日)京都大雨。(『京都気象災害年表』) ▣(12月12日)中務省火災、卿曹司の屋一間焼く。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(12月12日)中務省火災、卿曹司の屋一間焼く。(『三代実録』『日本災変通志』)
■864年(貞観6年) ▣ユ2月11日(1月1日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(1月25日)全国で疫病流行。「疫死百姓、国の申さざる無し」。祖税逃れの虚偽申告ありとも。(『三代実録』『疫病の古代史』) ▣(1月25日)全国で疫病流行。「疫死百姓、国の申さざる無し」。祖税逃れの虚偽申告ありとも。(『三代実録』『疫病の古代史』) ▣(3月11日)左京火事。民家3戸焼く。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(3月11日)左京火事。民家3戸焼く。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ7月2日(5月25日)京都霖雨。京師の隠居・飢病者に特に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ7月2日(5月25日)京都霖雨。京師の隠居・飢病者に特に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) 
■865年(貞観7年) ▣ユ5月1日(4月3日)京都降霜。(『京都気象災害年表』) ▣(5月13日)災疫を防ぐため神泉苑・七条大路・朱雀大路衢・東西で『般若心経』を読経、夜は佐比寺で疫神祭修し、災疫防がせる。(『三代実録』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(5月13日)災疫を防ぐため神泉苑・七条大路・朱雀大路衢・東西で『般若心経』を読経、夜は佐比寺で疫神祭修し、災疫防がせる。(『三代実録』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣ユ7月12日(6月16日)京都大風雨。民屋壊し樹木折る。建礼門の扉2枚倒れる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月12日(6月16日)京都大風雨。民屋壊し樹木折る。建礼門の扉2枚倒れる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣ユ8月12日(7月17日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月12日(7月17日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ8月26日(8月2日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月26日(8月2日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣(11月14日)左右京職は毎旬、弾正台は隔月、京中巡検を定める。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月14日)左右京職は毎旬、弾正台は隔月、京中巡検を定める。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』)
■866年(貞観8年) ▣(2月16日)穀価騰貴し、左右京白米・黒米の沽価定める。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(閏3月1日)京中貧窮者を鴨川辺に集め、銭・飯賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(閏3月10日)応天門の変で、夜、応天門・棲鳳楼・翔鸞楼焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(閏3月10日)応天門の変で、夜、応天門・棲鳳楼・翔鸞楼焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』)  ▣(閏3月22日)応天門火災のため百官を会して会昌門前で大祓。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(閏3月22日)応天門火災のため百官を会して会昌門前で大祓。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(閏3月)貧窮者を鴨川辺に集め、新銭5万文、飯2500褁を頒給する。(『京都事典』) ▣(閏3月)貧窮者を鴨川辺に集め、新銭5万文、飯2500褁を頒給する。(『京都事典』) ▣ユ5月-7月(4月-5月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月-7月(4月-5月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(5月19日)京師飢饉、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月19日)京師飢饉、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(6月28日)旱魃により飢民多く、京師人、東堀河の鮎魚を捕えて食らう。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(6月28日)旱魃により飢民多く、京師人、東堀河の鮎魚を捕えて食らう。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) 
■867年(貞観9年) ▣(2月3日)斎宮寮火、官舎12宇類焼。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(2月17日)東西京で、昨年の災害により米320石・籾20石・塩35斛・新銭100貫を飢民(乏絶)に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(2月17日)東西京で、昨年の災害により米320石・籾20石・塩35斛・新銭100貫を飢民(乏絶)に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(2月27日)近衛・兵衛、分番により京内夜行。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(2月27日)近衛・兵衛、分番により京内夜行。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(4月4日)太政官厨房北辺小宅失火、30余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月4日)太政官厨房北辺小宅失火、30余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(4月22日)米価安定のため、左右京に初めて常平所を置く。民間の穀価騰貴を救う。「東西京始置常平所、出官米而糶之、米一升直新銭八文、京邑之人来買者妙雲、是時穀価騰躍、内外飢饉、米一斛直新銭一千四百文、由是官糶以救俗幣焉」(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』) ▣(4月22日)米価安定のため、左右京に初めて常平所を置く。民間の穀価騰貴を救う。「東西京始置常平所、出官米而糶之、米一升直新銭八文、京邑之人来買者妙雲、是時穀価騰躍、内外飢饉、米一斛直新銭一千四百文、由是官糶以救俗幣焉」(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』) ▣ユ6月9日(5月4日)京都大雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月9日(5月4日)京都大雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(5月29日)京都疾疫流行。宮城京邑、病苦死喪者衆し、朱雀門前で大祓。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月29日)京都疾疫流行。宮城京邑、病苦死喪者衆し、朱雀門前で大祓。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(8月3日)これより先、左右京の乞索児宿屋を木工寮に造らせる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月3日)これより先、左右京の乞索児宿屋を木工寮に造らせる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ10月15日(9月14日)京都大風雨。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ10月15日(9月14日)京都大風雨。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) 
■868年(貞観10年) ▣ユ5月(5月26日)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣8月3日(7月8日)播磨・山城地震 「京都及諸國地大震、播磨殊甚」(『三代実録』)。「播磨・山城国大地震」、播磨国(兵庫県)の国府(現・姫路市)附近を震央とする地震(M7以上)、山崎断層の活動による。京都では官舎・寺塔倒壊、家屋被害、垣屋崩れる。(『日本被害地震総覧』『日本の自然災害』) ▣8月3日(7月8日)播磨・山城地震 「京都及諸國地大震、播磨殊甚」(『三代実録』)。「播磨・山城国大地震」、播磨国(兵庫県)の国府(現・姫路市)附近を震央とする地震(M7以上)、山崎断層の活動による。京都では官舎・寺塔倒壊、家屋被害、垣屋崩れる。(『日本被害地震総覧』『日本の自然災害』) ▣(8月17日)東宮坊より出火、数家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(8月17日)東宮坊より出火、数家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ8月22日(8月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月22日(8月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(12月7日)朱雀門前に貧窮者集め賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(12月7日)朱雀門前に貧窮者集め賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) 
■869年(貞観11年) ▣(1月25日)侍賢門扉火、夜。早く消し止む。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月14日(2月29日)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月14日(2月29日)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月24日(7月13日)京都落雷。武徳殿前。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月24日(7月13日)京都落雷。武徳殿前。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月5日(8月26日)京都大風雨。宮城、京邑の損傷甚だ多し。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ10月5日(8月26日)京都大風雨。宮城、京邑の損傷甚だ多し。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣この年、京都疾疫流行。神泉苑で御霊会が行われ、祇園会の始まりになる。この頃より901年まで京都で連年の霖雨。 ▣この年、京都疾疫流行。神泉苑で御霊会が行われ、祇園会の始まりになる。この頃より901年まで京都で連年の霖雨。  ⋄この年、山城旱魃とも。(『京都気象災害年表』) ⋄この年、山城旱魃とも。(『京都気象災害年表』)
■870年(貞観12年) ▣(2月24日)京都飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ7月12日(6月10日)京都白虹(霧虹)・霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月12日(6月10日)京都白虹(霧虹)・霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(6月17日)頻月淫霖雨。京都飢饉、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月17日)頻月淫霖雨。京都飢饉、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(7月29日)綴喜郡山本郷の山頽れ裂け陥る。相去る7丈に小山堆起す。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(7月29日)綴喜郡山本郷の山頽れ裂け陥る。相去る7丈に小山堆起す。(『三代実録』『日本災変通志』)
■871年(貞観13年) ▣ユ1月25日(1月1日)京都台風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ2月17日(1月24日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ2月17日(1月24日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ3月25日(3月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ3月25日(3月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(3月)京都霖雨。京都盗賊多し。近衛府官人に夜警させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月)京都霖雨。京都盗賊多し。近衛府官人に夜警させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ8月30日(8月11日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月30日(8月11日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ9月24日(閏8月7日)京都雷大雨水。洪水により道橋流出、民家も多く破壊されその数知らず。(『三代実録』『京都事典』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ9月24日(閏8月7日)京都雷大雨水。洪水により道橋流出、民家も多く破壊されその数知らず。(『三代実録』『京都事典』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ9月28日(閏8月11日)京都霖雨・洪水。平安京大洪水、「十一日甲寅。霖雨未止。東京居人遭水損者卅五(35)家百卅八(138)人。西京六百卅(630)家三千九百九十五人。」(『三代実録』)。雨やまず、水難者多数。左京35家138人、右京630家3995人に穀塩を与えた。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣ユ9月28日(閏8月11日)京都霖雨・洪水。平安京大洪水、「十一日甲寅。霖雨未止。東京居人遭水損者卅五(35)家百卅八(138)人。西京六百卅(630)家三千九百九十五人。」(『三代実録』)。雨やまず、水難者多数。左京35家138人、右京630家3995人に穀塩を与えた。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』)  ▣(閏8月14日)京都大雨・洪水。洪水対策のため、堤の築造・鴨川堤辺での水陸田耕営を禁じる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣(閏8月14日)京都大雨・洪水。洪水対策のため、堤の築造・鴨川堤辺での水陸田耕営を禁じる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』)  ▣(閏8月28日)百姓の葬送・放牧地は、山城国葛野郡・紀伊郡4カ所に限定される。(『三代実録』『日本史総合年表』) ▣翌年ユ1月31日(12月18日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(閏8月28日)百姓の葬送・放牧地は、山城国葛野郡・紀伊郡4カ所に限定される。(『三代実録』『日本史総合年表』) ▣翌年ユ1月31日(12月18日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■872年(貞観14年) ▣(1月20日)この月、京邑で咳病(咳逆病)流行、死者多数。渤海国より渤海使入国しており、「異土毒気(どくけ)」によるとの流言。建礼門前で大祓。(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『疫病の古代史』『平安京の災害史』『日本史総合年表』) ▣(2月)太政大臣・藤原良房が咳逆病患う。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(2月)太政大臣・藤原良房が咳逆病患う。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月21日(3月10日)京都大風雨。窮民に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ4月21日(3月10日)京都大風雨。窮民に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)   ▣ユ9月10日(8月4日)京都大風雨。民家多く倒れる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ9月10日(8月4日)京都大風雨。民家多く倒れる。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』)  
■873年(貞観15年) ▣ユ2月2日(1月1日)京都雷・飄(つむじ風)。(『京都気象災害年表』)  ▣(2月26日)東宮庁院1屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(2月26日)東宮庁院1屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ5月27日(4月27日)京都雷雹(あられ)。雷電、雹降る。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ5月27日(4月27日)京都雷雹(あられ)。雷電、雹降る。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣ユ6月1日(5月3日)京都雷雹。雹降る。大きさ鶏子・梅実の如し。賀茂神・松尾神の祟りとされ、両社に走馬を進献。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ6月1日(5月3日)京都雷雹。雹降る。大きさ鶏子・梅実の如し。賀茂神・松尾神の祟りとされ、両社に走馬を進献。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(6月22日)京邑・河内国など飢う。飢饉により倉廩を開き賑給。(『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(6月22日)京邑・河内国など飢う。飢饉により倉廩を開き賑給。(『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(7月9日)祈雨のため賀茂・稲荷・乙訓・貴布禰社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(7月9日)祈雨のため賀茂・稲荷・乙訓・貴布禰社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』)
■874年(貞観16年) ▣(4月19日)淳和院で火災。丑刻。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(閏4月12日)東の京、失火、庶人家焼く。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(閏4月12日)東の京、失火、庶人家焼く。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月6日)京邑飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月6日)京邑飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ6月18日(5月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月18日(5月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月30日(6月14日)京都雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月30日(6月14日)京都雷雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ10月8日(8月24日)京都大風雨(台風)・大洪水。平安京全域に洪水、鴨川・桂川氾濫。紫宸殿前・東宮・侍従局などの樹木倒木、内外官舎・人民盧舎全きもの稀。京都付近の河々7-8尺暴漲、城下直撃し、大小橋全て落ちる。朱雀大路豊財坊門倒壊、4人圧死。東西河川氾濫し百姓牛馬溺没、死者数を知らず。淀の渡し付近30余家・山崎橋付近40余家、人とともに流失。この前後-900年にかけて京都では長雨洪水が頻発。(『三代実録』『皇年略記』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本の自然災害』『日本史総合年表』) ▣ユ10月8日(8月24日)京都大風雨(台風)・大洪水。平安京全域に洪水、鴨川・桂川氾濫。紫宸殿前・東宮・侍従局などの樹木倒木、内外官舎・人民盧舎全きもの稀。京都付近の河々7-8尺暴漲、城下直撃し、大小橋全て落ちる。朱雀大路豊財坊門倒壊、4人圧死。東西河川氾濫し百姓牛馬溺没、死者数を知らず。淀の渡し付近30余家・山崎橋付近40余家、人とともに流失。この前後-900年にかけて京都では長雨洪水が頻発。(『三代実録』『皇年略記』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本の自然災害』『日本史総合年表』)  ▣(9月7日)東西京の風水損を激しく受けた3159家に賑給。(『三代実録』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(9月7日)東西京の風水損を激しく受けた3159家に賑給。(『三代実録』『京都事典』『日本災変通志』)   ▣翌年ユ1月29日(12月19日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月29日(12月19日)京都大雪。(『京都気象災害年表』)
■875年(貞観17年) ▣(1月28日)冷泉院火災、収蔵書籍・財宝灰燼。延焼54宇。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本史総合年表』) ▣(5月12日)旋風風、紫宸殿前。木工寮失火、官人宿直舎1屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月12日)旋風風、紫宸殿前。木工寮失火、官人宿直舎1屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ7月10日(6月4日)京都降雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月10日(6月4日)京都降雪。(『京都気象災害年表』) ▣(6月24日)数旬にわたり雨降らず。神泉苑の池水決出。鐘鼓歌舞を催し降雨祈る。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(6月24日)数旬にわたり雨降らず。神泉苑の池水決出。鐘鼓歌舞を催し降雨祈る。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(6月)京都大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(6月)京都大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(6月-7月)京都大旱、神泉苑の池水を放出、歌舞を催し祈雨。請雨経法が国家事業として修された。 ▣(6月-7月)京都大旱、神泉苑の池水を放出、歌舞を催し祈雨。請雨経法が国家事業として修された。 ▣ユ8月14日-16日(7月10日-12日/7月10日)京都雷電大雨・大雷雨。樹木・民家倒れる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ8月14日-16日(7月10日-12日/7月10日)京都雷電大雨・大雷雨。樹木・民家倒れる。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) 
■876年(貞観18年) ▣(1月3日)霧により暗し、西ノ京三条。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ4月19日(3月21日)京都霖雨・賑給。人々飢う、賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(4月10日)大極殿火災、初めて焼失し、小安殿・延休堂など100余間焼失し数日間延焼。賀茂祭止む。(『三代実録』『日本王代一覧』『皇年代略記』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(4月10日)大極殿火災、初めて焼失し、小安殿・延休堂など100余間焼失し数日間延焼。賀茂祭止む。(『三代実録』『日本王代一覧』『皇年代略記』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣(4月27日)近衛・兵衛などを遣わし左右京を夜行させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(4月27日)近衛・兵衛などを遣わし左右京を夜行させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ6月7日(5月12日)京都台風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月7日(5月12日)京都台風。(『京都気象災害年表』) ▣(5月)京都霖雨・賑給。(『京都気象災害年表』) ▣(5月)京都霖雨・賑給。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ6月28日(6月4日)京都冷気。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月28日(6月4日)京都冷気。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月1日(6月7日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月12日(6月18日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月1日(6月7日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月12日(6月18日)京都降雹。(『京都気象災害年表』) ▣7月13日(6月19日)この頃、京都飢饉のため賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣7月13日(6月19日)この頃、京都飢饉のため賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月29日)第57代・陽成天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ8月14日(7月21日)京都雲なく雷。(『京都気象災害年表』) ▣(6月29日)第57代・陽成天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ8月14日(7月21日)京都雲なく雷。(『京都気象災害年表』) ▣(8月26日)東ノ京失火、民2家焼く。夜。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(8月26日)東ノ京失火、民2家焼く。夜。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(11月3日)大舎人寮の倉屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月3日)大舎人寮の倉屋焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ12月25日(12月6日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月25日(12月6日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』)  ▣疫病流行る。牛頭天王を東山八坂に祀る前に梛の森に仮祭祀。 ▣疫病流行る。牛頭天王を東山八坂に祀る前に梛の森に仮祭祀。 ▣この年 京師・畿内諸国・亢旱、近年丹後国、水旱、百姓飢餓。公卿僉議(評議)、東西京中に常平司置き官米出売り、河内・和泉国絶乏戸に賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣この年 京師・畿内諸国・亢旱、近年丹後国、水旱、百姓飢餓。公卿僉議(評議)、東西京中に常平司置き官米出売り、河内・和泉国絶乏戸に賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) 
■877年(貞観19年/元慶元年) ▣(1月27日)畿内飢饉のため、東西京中に常平司(所)を置き官米を売る。賑給する(『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣(2月15日)牧童の失火により北野を焼く。山嶺延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(2月15日)牧童の失火により北野を焼く。山嶺延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(3月11日)京都地震。辰刻、大震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(3月11日)京都地震。辰刻、大震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月14日(6月)近畿大旱。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月14日(6月)近畿大旱。(『京都気象災害年表』) ▣(7月10日)旱魃のため神泉苑の水を引き、城南の民田に灌漑する。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(7月10日)旱魃のため神泉苑の水を引き、城南の民田に灌漑する。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(10月17日)京地地震。大震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(10月17日)京地地震。大震。(『三代実録』『日本災変通志』) 防鴨河使を議定し、平随時を任命する。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) 防鴨河使を議定し、平随時を任命する。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ12月17日(11月9日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月17日(11月9日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(11月21日)左衛士の居坊失火、夜、延焼7家。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(11月21日)左衛士の居坊失火、夜、延焼7家。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣畿内で大旱、飢饉。 ▣畿内で大旱、飢饉。 
■878年(元慶2年) ▣(1月28日)左右京に売常司を置き売常平所米使を定めた。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(1月)京都、盗賊横行。近衛官人、夜行させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(1月)京都、盗賊横行。近衛官人、夜行させる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(2月10日)京都飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(2月10日)京都飢う、賑給。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(2月27日)盗賊、紫宸殿軟障剥ぎ取り、近衛に捕えられる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』) ▣(2月27日)盗賊、紫宸殿軟障剥ぎ取り、近衛に捕えられる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)  ▣ユ5月14日(4月9日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣(5月-7月)畿内旱魃・飢饉。 ▣ユ5月14日(4月9日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣(5月-7月)畿内旱魃・飢饉。  ▣ユ7月6日(6月3日)山城旱魃。昨年より亢旱のため祈雨で賀茂二社・松尾・稲荷・貴布禰・乙訓など8社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月6日(6月3日)山城旱魃。昨年より亢旱のため祈雨で賀茂二社・松尾・稲荷・貴布禰・乙訓など8社に奉幣。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月19日(6月16日)京都大雷・雨水・電雨。京城の溝暗渠など皆溢れ、東寺幡竿に落雷。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月19日(6月16日)京都大雷・雨水・電雨。京城の溝暗渠など皆溢れ、東寺幡竿に落雷。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣ユ8月2日(7月1日)京都落雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月2日(7月1日)京都落雷。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月18日(8月18日)京都大風雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月18日(8月18日)京都大風雨・洪水。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ10月20日(9月21日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月20日(9月21日)京都雨水。(『京都気象災害年表』) ▣(9月29日)京都地震。夜に地震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(9月29日)京都地震。夜に地震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(9月)京都洪水頻発。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(9月)京都洪水頻発。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)
■879年(元慶3年) ▣ユ2月4日(1月10日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(2月13日)左京失火。民家数戸焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(2月13日)左京失火。民家数戸焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(3月22日)京都地震。丑一刻、地大振動。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(3月22日)京都地震。丑一刻、地大振動。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月11日(6月18日)京都大雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月11日(6月18日)京都大雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(6月19日)東西京の飢饉病困者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(6月19日)東西京の飢饉病困者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(8月30日)西京(右京)一条火災、10余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(8月30日)西京(右京)一条火災、10余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(9月25日)九条坊門小路の東の鴨川辛(唐)橋が大半焼け断つ。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(9月25日)九条坊門小路の東の鴨川辛(唐)橋が大半焼け断つ。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)
■880年(元慶4年) ▣(4月2日)京都地大震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月22日)京都大雨。苗稲(稼)水没しかけ神泉苑で止雨祈願。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(5月22日)京都大雨。苗稲(稼)水没しかけ神泉苑で止雨祈願。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣(12月4日)京都大地震。子時、地大震動、夜より旦迄16度震う。大極殿西北隅、堅檀長石8間破裂、宮城墻垣、京師盧舎、頽損する者往々甚だ衆し。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(12月4日)京都大地震。子時、地大震動、夜より旦迄16度震う。大極殿西北隅、堅檀長石8間破裂、宮城墻垣、京師盧舎、頽損する者往々甚だ衆し。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣翌年ユ1月9日・グ1月13日(12月6日)京都地震。子刻。М6.4。夜より旦まで16度震う。宮城の大極殿西北隅、堅壇長石8間破裂、垣墻(えんしょう、垣)・官庁・民家の頽損多く、余震は翌年(1・2月)まで続く。京都盆地中心の地震か?。「地震の徴、兵賊飢疫を慎むべし」(「勘文」)(『三代実録』『類聚国史』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『平安京の災害史』『日本被害地震総覧』「 ▣翌年ユ1月9日・グ1月13日(12月6日)京都地震。子刻。М6.4。夜より旦まで16度震う。宮城の大極殿西北隅、堅壇長石8間破裂、垣墻(えんしょう、垣)・官庁・民家の頽損多く、余震は翌年(1・2月)まで続く。京都盆地中心の地震か?。「地震の徴、兵賊飢疫を慎むべし」(「勘文」)(『三代実録』『類聚国史』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『平安京の災害史』『日本被害地震総覧』「 地震インフォ」) 地震インフォ」)
■881年(元慶5年) ▣(1月27日)京都大雪大風。夜、東ノ京に火、人居6家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)   ▣ユ3月2日(1月28日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ3月2日(1月28日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(3月23日)京都、飢窮病困者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月23日)京都、飢窮病困者に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ7月13日(6月14日)京都霖雨・賑給。(1日)より霖雨続き困乏者に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣ユ7月13日(6月14日)京都霖雨・賑給。(1日)より霖雨続き困乏者に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『日本災変通志』)  ▣ユ12月12日(11月18日)京都新雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月12日(11月18日)京都新雪。(『京都気象災害年表』)
■882年(元慶6年) ▣ユ1月23日(1月1日)京都大雪。2尺。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月18日(5月29日/5月)京都霖雨・賑給。貧困病者に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ6月18日(5月29日/5月)京都霖雨・賑給。貧困病者に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣(9月25日)大膳職醤を焼く。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(9月25日)大膳職醤を焼く。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) 
■883年(元慶7年) ▣ユ5月7日(3月27日)京都大雨洪水。左京飢民に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)   ▣(5月25日)山崎橋火、夜、1間焼く。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(5月25日)山崎橋火、夜、1間焼く。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月8日(6月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月8日(6月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月5日(9月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月5日(9月)京都霖雨。(『京都気象災害年表』) ▣(11月29日)図書寮1倉1屋、失火焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(11月29日)図書寮1倉1屋、失火焼亡。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) 
■884年(元慶8年) ▣ユ2月2日(1月2日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ2月4日(1月4日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣(2月5日)第58代・光孝天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)
▣ユ3月25日(2月25日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月3日(3月4日)京都廻颷(つむじ風)。旋風、左儀頭の火焚小屋を壊す。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ2月4日(1月4日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣(2月5日)第58代・光孝天皇践祚。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)
▣ユ3月25日(2月25日)京都大霧。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月3日(3月4日)京都廻颷(つむじ風)。旋風、左儀頭の火焚小屋を壊す。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(3月15日)大雷雨、夜、常住寺(野寺)塔に落雷、五層より延焼、講堂・金堂・鐘楼・経蔵など焼亡。(『三代実録』『類聚国史』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月15日)大雷雨、夜、常住寺(野寺)塔に落雷、五層より延焼、講堂・金堂・鐘楼・経蔵など焼亡。(『三代実録』『類聚国史』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』)   ▣(3月22日)左右京飢民に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月22日)左右京飢民に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ4月25日(3月26日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ4月25日(3月26日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月3日(4月5日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月3日(4月5日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ5月9日(4月11日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月9日(4月11日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月12日(4月14日)京都風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月12日(4月14日)京都風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ5月14日(4月16日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月14日(4月16日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月15日(4月17日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月15日(4月17日)京都晩霜。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月21日(7月27日)山城雷雨。愛宕郡委穀倉一宇に落雷焼失。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ8月21日(7月27日)山城雷雨。愛宕郡委穀倉一宇に落雷焼失。(『三代実録』『日本災変通志』)  ▣ユ10月10日(9月18日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月10日(9月18日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』)  ▣本年より3年間、京都に飢民多い。 ▣本年より3年間、京都に飢民多い。
■885年(元慶9年/仁和元年) ▣(2月18日)京都大火、夜。東ノ京左京一条衛士町で失火、300余戸類焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『平安京の災害史』) ▣ユ5月8日(閏3月20日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月8日(閏3月20日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ6月30日(5月14日)京都霖雨・飢饉。(『京都気象災害年表』) ▣ユ6月30日(5月14日)京都霖雨・飢饉。(『京都気象災害年表』)  ▣(5月20日)京都霖雨により飢民に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月20日)京都霖雨により飢民に賑給。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』)  ▣翌年ユ1月22日(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月22日(12月14日)京都大雪。(『京都気象災害年表』) ▣(12月27日)京都大火。西ノ京右京二条で出火、200余戸類焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(12月27日)京都大火。西ノ京右京二条で出火、200余戸類焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』)
■886年(仁和2年) ▣(2月20日)山崎津頭失火、延焼居民盧舎数十/十数宇。(『三代実録』『類聚国史』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣(3月8日)京都大風雨雷。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(3月8日)京都大風雨雷。(『三代実録』『日本災変通志』)   ▣ユ4月20日(3月13日)京都大雷雨。暴風雷雨、東寺新造塔が雷火により焼亡。?。東大寺?(『三代実録』『興福寺略年代記』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』) ▣ユ4月20日(3月13日)京都大雷雨。暴風雷雨、東寺新造塔が雷火により焼亡。?。東大寺?(『三代実録』『興福寺略年代記』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』『日本歴史災害事典』『日本史総合年表』)    ▣(3月20日)京都雷雨、歩行の女震死。 (『三代実録』『日本災変通志』) ▣(3月20日)京都雷雨、歩行の女震死。 (『三代実録』『日本災変通志』)  ▣ユ5月25日(4月18日)京都陰寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月25日(4月18日)京都陰寒。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月27日(4月20日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ5月27日(4月20日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ6月15日(5月10日)京都大雨。(7日)より大雨、河水漲溢し人馬通ぜず。(『三代実録』『京都気象災害年表『日本災変通志』) ▣ユ6月15日(5月10日)京都大雨。(7日)より大雨、河水漲溢し人馬通ぜず。(『三代実録』『京都気象災害年表『日本災変通志』) ▣(5月26日)石清水八幡宮、自鳴。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月18日(6月13日)京都霖雨・飢饉。(1日)より霖雨、飢困に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』) ▣(5月26日)石清水八幡宮、自鳴。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月18日(6月13日)京都霖雨・飢饉。(1日)より霖雨、飢困に賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『日本災変通志』)  ▣ユ9月8日(8月7日)京都大風雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月8日(8月7日)京都大風雨・洪水。(『京都気象災害年表』)  ▣(8月12日)京都大火。右京衛士居坊失火、100余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣(8月12日)京都大火。右京衛士居坊失火、100余家延焼。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』『平安京の災害史』) ▣ユ10月4日(9月4日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月4日(9月4日)京都大雷雨。(『京都気象災害年表』) 
■887年(仁和3年) ▣(2月1日)盗人、正蔵院に入り官物を取る。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(5月14日)唐橋に初めて橋守置く。山城国徭丁を充てる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ7月5日(6月11日)京都霖雨・飢饉。(5月)より霖雨、左右京飢民に倉廩を開いて賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』) ▣(5月14日)唐橋に初めて橋守置く。山城国徭丁を充てる。(『三代実録』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ7月5日(6月11日)京都霖雨・飢饉。(5月)より霖雨、左右京飢民に倉廩を開いて賑給。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本災変通志』)  ▣ユ7月21日(6月27日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月21日(6月27日)京都雷雹。(『京都気象災害年表』)  ▣(7月2日)京都地震。夜に地震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(7月2日)京都地震。夜に地震。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ7月29日・グ8月2日(7月6日)京都地震。(M6.5)?。「京都及諸國地大震海嘯、摂津殊甚」(『三代実録』)。越後西部で津波による溺死者多数。 ▣ユ7月29日・グ8月2日(7月6日)京都地震。(M6.5)?。「京都及諸國地大震海嘯、摂津殊甚」(『三代実録』)。越後西部で津波による溺死者多数。 ▣ユ8月22日・グ8月26日(7月30日)京都大地震。「仁和南海地震」「仁和地震」「五畿・七道地震」、京都市震度5強、(M8.0-8.5/8.3)。震央は南海トラフ。西日本太平洋側、南海トラフ沿いの巨大地震、五畿内七道諸国震る。近畿沿岸に海潮(かいちょう、津波)陸に漲(みなぎ)る。溺死多数、中摂津国の被害もっとも甚し。同時期に東南海・東海地震も発生。京都・摂津を中心に死者多数。京都でも有感、余震続く。申時、亥刻3度震う。京都で諸司倉屋、東西京盧舎、百姓宅など顛覆。圧死者多く、失神者・頓死者あり。(『日本紀略』『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本歴史災害事典』『平安京の災害史』『日本被害地震総覧』『日本の自然災害』『日本史総合年表』「 ▣ユ8月22日・グ8月26日(7月30日)京都大地震。「仁和南海地震」「仁和地震」「五畿・七道地震」、京都市震度5強、(M8.0-8.5/8.3)。震央は南海トラフ。西日本太平洋側、南海トラフ沿いの巨大地震、五畿内七道諸国震る。近畿沿岸に海潮(かいちょう、津波)陸に漲(みなぎ)る。溺死多数、中摂津国の被害もっとも甚し。同時期に東南海・東海地震も発生。京都・摂津を中心に死者多数。京都でも有感、余震続く。申時、亥刻3度震う。京都で諸司倉屋、東西京盧舎、百姓宅など顛覆。圧死者多く、失神者・頓死者あり。(『日本紀略』『三代実録』『京都の歴史10
年表・事典』『京都事典』『日本歴史災害事典』『平安京の災害史』『日本被害地震総覧』『日本の自然災害』『日本史総合年表』「 地震インフォ」) 地震インフォ」) ▣(8月朔)京都地震。京都昼夜地震2度、(2日)昼3度、(4日)5度、(5日)昼地震5度、夜に大震、京師の人民、屋舎より出て街路に居る。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣(8月朔)京都地震。京都昼夜地震2度、(2日)昼3度、(4日)5度、(5日)昼地震5度、夜に大震、京師の人民、屋舎より出て街路に居る。(『三代実録』『日本災変通志』) ▣ユ9月12日(8月20日)京都大風雨・洪水。民家多く倒れ賀茂川、葛野川など氾濫。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』) ▣ユ9月12日(8月20日)京都大風雨・洪水。民家多く倒れ賀茂川、葛野川など氾濫。(『三代実録』『京都気象災害年表』『京都の歴史10 年表・事典』『京都事典』)  ▣(8月26日)第59代・宇多天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月)京都大雨・洪水。悲田院の病人300人流される。 ▣(8月26日)第59代・宇多天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(8月)京都大雨・洪水。悲田院の病人300人流される。
■888年(仁和4年) ▣ユ3月4日(1月18日)京都飃風(つむじ風)、未刻、東二条院で樹木折り人屋損ず。(『日本紀略』『京都気象災害年表』『日本災変通志』) ▣(2月3日)侍賢門南扉、故なく顛倒。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(2月3日)侍賢門南扉、故なく顛倒。(『日本紀略』『日本災変通志』)  ▣ユ9月11日(8月2日)京都降雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ9月11日(8月2日)京都降雪。(『京都気象災害年表』)
■889年(仁和5年/寛平元年) ▣ユ5月13日(4月10日)京都風雨・雷雹。雷鳴、碁石大の雹降る。(『京都気象災害年表』『日本災変通志』)    ▣(6月/6月-7月)京都霖雨・洪水、餓死者多数。(『山城志』『扶桑略記』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月/6月-7月)京都霖雨・洪水、餓死者多数。(『山城志』『扶桑略記』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ8月1日(7月)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月1日(7月)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』)
■890年(寛平2年) ▣ユ7月6日・グ7月10日(6月16日)京都地震。М6.0。舎屋傾き、ほとんど倒潰寸前のものあり。(『日本被害地震総覧』「 地震インフォ」) 地震インフォ」) ▣ユ12月6日(10月21日)京都初雪。(『京都気象災害年表』) ▣ユ12月6日(10月21日)京都初雪。(『京都気象災害年表』) ▣(11月29日)使を遣わし、京中盗賊捜索。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月29日)使を遣わし、京中盗賊捜索。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣珍皇寺焼亡。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣珍皇寺焼亡。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)
■891年(寛平3年) ▣ユ6月10日(5月)京都旱魃。(『京都気象災害年表』) ▣(6月2日・16日・18日)祈雨のため、京畿諸寺に仁王般若経を転読させ諸社に奉幣。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月2日・16日・18日)祈雨のため、京畿諸寺に仁王般若経を転読させ諸社に奉幣。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月26日)旱災により、左右獄囚1人放出。(『日本災変通志』) ▣(6月26日)旱災により、左右獄囚1人放出。(『日本災変通志』) ▣(7月7日)宮城付近の山、連日火事。修理職・諸衛府に防がせる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(7月7日)宮城付近の山、連日火事。修理職・諸衛府に防がせる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣翌年ユ1月19日(12月16日)京都大雪。2尺。(『京都気象災害年表』) ▣翌年ユ1月19日(12月16日)京都大雪。2尺。(『京都気象災害年表』)
■892年(寛平4年) ▣(2月29日)常平所門扉、人を圧し死者10余人。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』) ▣ユ8月29日(8月4日)京都虹是歳京都大雪3尺。(『京都気象災害年表』) ▣この年、京都大雪。積雪一丈(1m)。(『日本紀略』) ▣ユ8月29日(8月4日)京都虹是歳京都大雪3尺。(『京都気象災害年表』) ▣この年、京都大雪。積雪一丈(1m)。(『日本紀略』)
■893年(寛平5年) ▣この年、百姓らの鴨川堤辺での耕作禁じ、防鴨河使所、勘収(取調・没収)する。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』)
■894年(寛平6年) ▣(3月24日)京都、地震2度。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(11月30日)検非違使に大井・与度・山崎・大津などを巡察させる。(『政事要略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(11月30日)検非違使に大井・与度・山崎・大津などを巡察させる。(『政事要略』『京都の歴史10 年表・事典』) 
■895年(寛平7年) ▣(5月13日)洪水により貴布禰社・丹生川上神に奉幣。 (『日本紀略』『日本災変通志』) ▣ユ8月3日(7月9日)京都洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ8月3日(7月9日)京都洪水。(『京都気象災害年表』)
■896年(寛平8年) ▣(閏1月17日)左右看督・近衛ら旬毎に施薬院(九条坊門南、西洞院東)・東西悲田院の病人・孤児を巡検する。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(4月13日)鴨川東西の堤耕作許す。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ6月23日(5月9日)京都洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(4月13日)鴨川東西の堤耕作許す。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣ユ6月23日(5月9日)京都洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(8月21日)霖雨により鴨下社などに奉幣、止雨祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(8月21日)霖雨により鴨下社などに奉幣、止雨祈願。(『日本紀略』『日本災変通志』)
■897年(寛平9年) ▣(4月10日)賀茂祭の騎兵役拒否の土人・浪人罰する。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣ユ7月-8月(6月-7月)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月-8月(6月-7月)京都霖雨・洪水。(『京都気象災害年表』) ▣(7月3日)第60代・醍醐天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣この年、京都霖雨洪水、両京飢餓多し。(『扶桑略記』『日本災変通志』) ▣(7月3日)第60代・醍醐天皇践祚。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣この年、京都霖雨洪水、両京飢餓多し。(『扶桑略記』『日本災変通志』) 
■898年(寛平10年/昌泰元年) ▣(3月-4月)京中、外国癘疫の消すため諸社に奉幣、15大寺に金剛般若経1万巻転読。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣ユ7月3日(5月22日)京都飄風(つむじ風)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月3日(5月22日)京都飄風(つむじ風)。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月26日(6月15日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』) ▣ユ7月26日(6月15日)京都大風雨。(『京都気象災害年表』)  ▣ユ8月10日(7月1日)京都黄霧。(『京都気象災害年表』) ▣(7月8日)疾病疫により、諸国より上京する相撲人を停む。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣ユ8月10日(7月1日)京都黄霧。(『京都気象災害年表』) ▣(7月8日)疾病疫により、諸国より上京する相撲人を停む。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月27日)京都大地震。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(7月27日)京都大地震。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣ユ10月16日(9月8日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣ユ10月16日(9月8日)京都大風。(『京都気象災害年表』) ▣この年-翌年、京近畿群盗横行・蜂起。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』) ▣この年-翌年、京近畿群盗横行・蜂起。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本災変通志』『日本史総合年表』)
■899年(昌泰2年) ▣(1月28日)太政官厨家失火。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(2月1日)京中群盗蜂起、四衛府官人に巡察させる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』) ▣(2月1日)京中群盗蜂起、四衛府官人に巡察させる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』『日本史総合年表』)  ▣(2月13日)左右検非違使に野宮の群盗捜索させる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(2月13日)左右検非違使に野宮の群盗捜索させる。(『日本紀略』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(5月22日) 瓢(つむじ)風、大極殿の高御座巽に傾き、中務省正庁傾く。京中人家破れざる稀。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(5月22日) 瓢(つむじ)風、大極殿の高御座巽に傾き、中務省正庁傾く。京中人家破れざる稀。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月4日)左右京職に結保帳に基づき京中乱行巡察させる。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』) ▣(6月4日)左右京職に結保帳に基づき京中乱行巡察させる。(『類聚三代格』『京都の歴史10 年表・事典』)  ▣(6月15日)京都大風雨。木を折り屋発く。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣(6月15日)京都大風雨。木を折り屋発く。(『日本紀略』『日本災変通志』)  ▣昨年より 京近畿群盗蜂起、人家焼き人を殺す。(『日本紀略』『日本災変通志』) ▣昨年より 京近畿群盗蜂起、人家焼き人を殺す。(『日本紀略』『日本災変通志』) 
|
 地震・津波 地震・津波  大雨・長雨・洪水 大雨・長雨・洪水  台風・大風など 台風・大風など  雷 雷  旱魃・酷暑 旱魃・酷暑  大雪・雹・寒冷など 大雪・雹・寒冷など  山崩・土砂崩 山崩・土砂崩  凶作・不作 凶作・不作  虫害・獣害 虫害・獣害  飢饉・窮乏・賑給 飢饉・窮乏・賑給  疫病・疾病など 疫病・疾病など  火災 火災  戦乱・一揆・強訴 戦乱・一揆・強訴  事件・事故など 事件・事故など  公害・環境 公害・環境  土木など 土木など
⇒古墳時代 ⇒飛鳥時代 ⇒奈良時代 ⇒平安時代前期
1 古墳時代-平安時代前期 2 平安時代中期 3 平安時代後期 1 4 平安時代後期 2 5 鎌倉時代 1 6 鎌倉時代 2 7 南北朝時代 8 室町時代前期 9 室町時代中期 10 室町時代後期 11 安土・桃山時代 12 江戸時代前期 13 江戸時代中期 14 江戸時代後期 15 近代 16 現代
*京都を中心にした主な事項と、京都と関係深い延暦寺・園城寺(三井寺)関連も記述しています。自然災害は被害が生じた・生じたとみられるものに限定しています。災害に人災である戦乱・騒乱なども含め、それら種々の被災に対する政策、背景の主な政治・社会の動き・祭礼などについても記しました。各事象について後世の言及・論証があるものについては記しました。怪異現象の多くは省きました。時代区分は諸説あり、コンテンツ容量調整のための便宜的なものです。災害のカテゴリ色分けは厳密なものではなく、含まれないものもあります。用語の統一は行っていません。現在は使われていない用語も、歴史的な表現としてそのまま記しています。データベースは特性上、常に作成状態にあります。内容の精確向上のため入力・更新は続けていますが、当ウェブサイトで得られた情報によるいかなる不利益に対しても対応できませんのでその点は御了承ください。
*旧暦(太陰太陽暦)・新暦(太陽暦)について、ユリウス暦・グレゴリオ暦・旧暦などの併記は、非常に煩雑になるため、近代以前は基本を旧暦で統一しています。各変換の詳細についてはこちらへ。国立天文台 日本の暦日データベース
*参考文献・資料 『日本災変通志』(2004)、『京都の歴史10 年表・事典』(1976)、『京都事典』(1979)、『京都気象災害年表』(1951)、『日本史総合年表』(2001)、『日本の自然災害』、『日本被害地震総覧』、『日本史年表増補版』、『京都大事典』、『日本災害史2 地震・津波』、『日本災害史3 気象』、『20世紀日本大災害の記録』、『日本史小百科 災害』、『京都の歴史災害』、『疫病の古代史』、『平安京の災害史』、『貴族日記が描く京の災害』、『災害と生きる中世』、『中世 災害・戦乱の社会史』、『江戸の災害史』、『日本災害史』、『京の火事物語』、『京都の災害をめぐる』、『日本歴史災害事典』、『日本年号史大事典』、「特別展京の災害-地震と火事-」、ウェブサイト「都市史-京都市」、ウェブサイト「京都市情報館」、ウェブサイト「京都市消防局」、ウェブサイト「京都府建設交通部砂防課」、ウェブサイト「京都地方気象台」、ウェブサイト「地震調査研究推進本部事務局-文部科学省研究開発局地震・防災研究課」、ウェブサイト「地震インフォ」、ウェブサイト「国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所」、ウェブサイト「京都府健康福祉部」、ウェブサイト「防災情報新聞」、ウェブサイト「天理大学」、ウェブサイト「東京大学史料編纂所『日本中世気象災害史年表稿』」、ウェブサイト「奈良文化財研究所データベース」、ウェブサイト「コトバンク」、ウェブサイト「Wikipedia」
                                    |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
   |
   |
 ©2006- Kyotofukoh,京都風光 ©2006- Kyotofukoh,京都風光 |
京都歴史災害年表 1
|
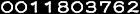 |



